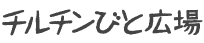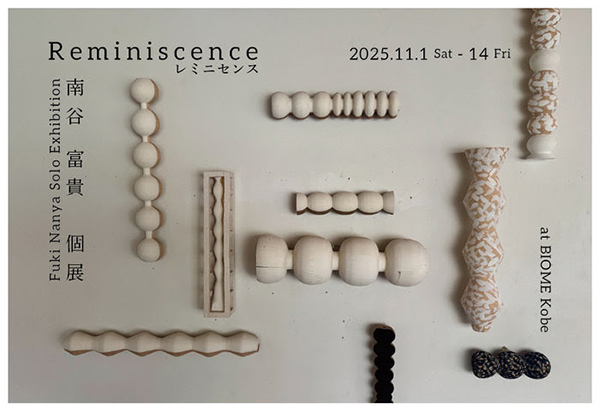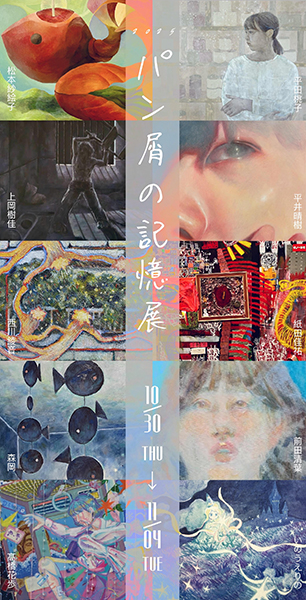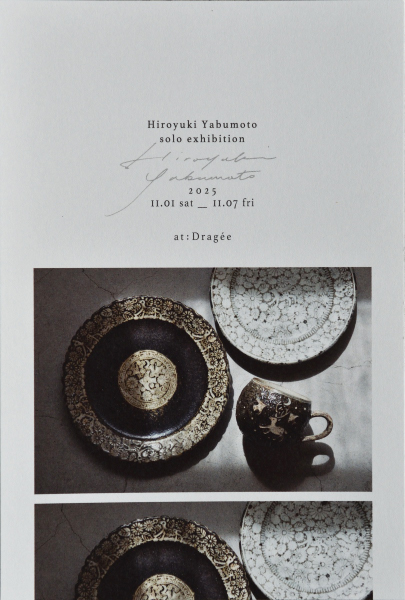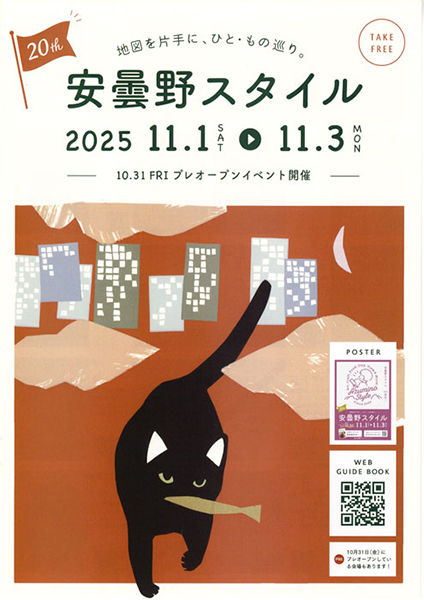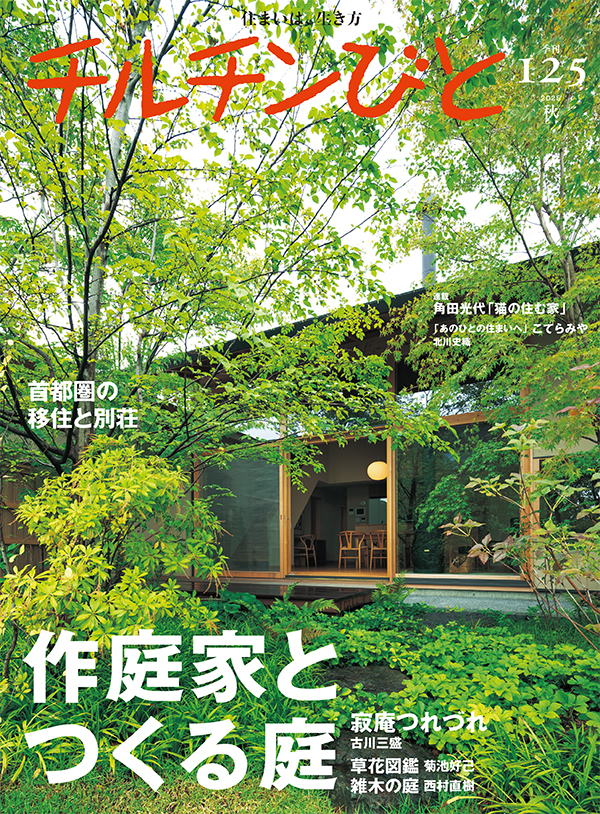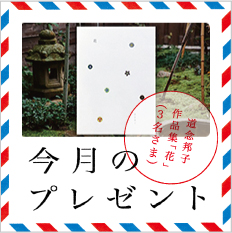7月28日(月)
「なにわの日」講演会

今から52年前の1973年7月28日、難波宮なにわのみやの発見と保存運動に生涯を捧げたひとりの考古学者、山根徳太郎博士が亡くなりました。
この功績を顕彰し、大阪の歴史と文化を語る講演会を開催します。
今年のテーマは難波宮です。
難波宮に関心のある方も、初めて知ったという方も、多くのご参加をお待ちしています。
講演内容 1.よみがえる古代の都―難波宮跡・内裏地区の発掘と公園の整備について 田中 裕子(大阪歴史博物館学芸員) 2025 年3 月、史跡難波宮跡の北部に位置する内裏地区が新たに史跡公園として公開されました。かつて天皇の住まいや政治の中枢が置かれていたとされるこの場所では、公園整備に先立ち発掘調査が行われ、前期難波宮(飛鳥時代)の建物跡など貴重な発見がありました。発掘で明らかになった古代の都・難波宮の姿や、新しく整備された公園内での遺構の見せ方、散策の楽しみ方などをご紹介します。 2.後期難波宮と聖武天皇 積山 洋氏(大阪公立大学客員教授) 奈良時代のスーパースター・聖武天皇はいかなる想いで難波宮を再建したのでしょうか? 難波の地にどんな想いを寄せていたのでしょうか?平城宮、恭仁宮、紫香楽宮などに比べて後期難波宮はいかなる姿だったのか? 人々が住んだ難波京はどんな姿だったのか? いろいろな角度から奈良時代の難波宮を考えてみたいと思います。