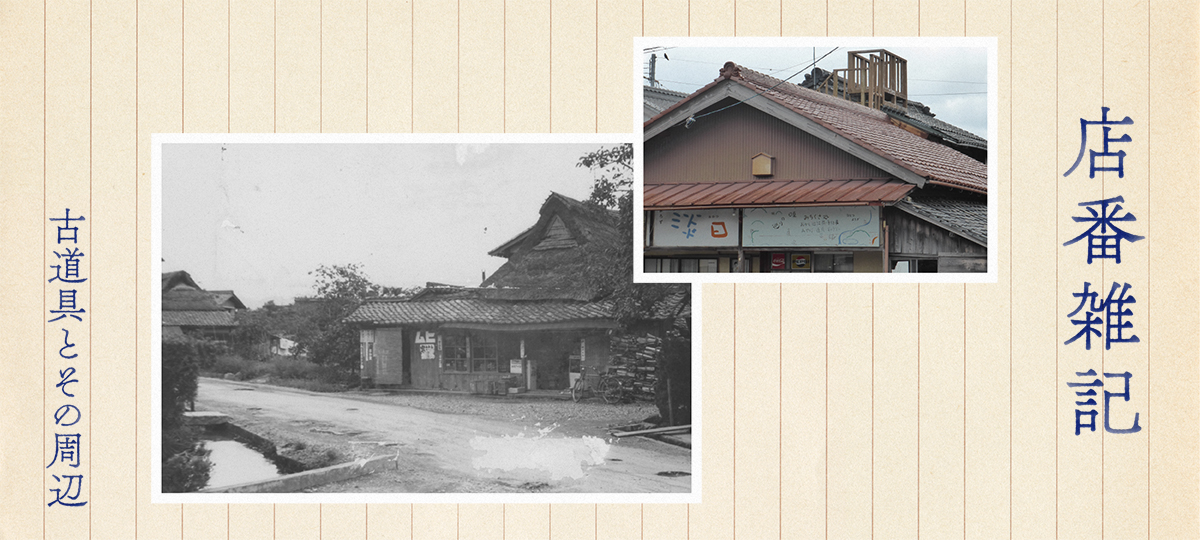彦根の商店街の夏の出店「山の湯夜市」で、おいしい冷やしかぼちゃを食べた。聞くと、小学生の女の子が、多賀町敏満寺にある料理屋・藤家さんで教わってきたという。その店では夏の2か月だけ多賀蕎麦を出しているというので、いそいそ出かけた。
メニューにはテイクアウトの鮒ずしもあった。彦根に来てからは正月に鮒ずしを頂いているが、お気に入りの味の店ではよい鮒が手に入らなくなったからと、最近は作らなくなった。その後はなかなか好みの鮒ずしには出会えない。そんなことを話していたら、店の人に「鮒ずし、作らへん?」とふわっと言われた。
鮒ずしは滋賀の郷土料理で、独特な匂いと味の鮒のなれずし。春に獲れた鮒を下処理して塩漬け、夏に本漬けをして冬越しさせる。匂いが強いので(でもくさやには負ける)、誰にも好まれるとは言えないが、日本酒好きにはよいアテになると思う。
鮒ずし作りの先生は「作りたくなってきた?」と、蕎麦を運びながらまたふわっと言う。「小さなバケツぐらいでもいけるよ」と軽く押される。「道具とか全部あるし。来るだけでいいから」。家に戻って考えて、これも何かの縁、と作ってみることにした。
初日は鮒ずしの本漬けから。通常メス・オス半分ずつで計5~6キロが多いそうだが、私は少しだけメスを入れてもらって最小の3キロ、小さめ11匹。
まず塩漬けした鮒を洗う作業、塩切り。ブラシで鮒を磨き洗いし、口やエラの中のひっかかるものを取り、よく塩を洗い流す。次に内側を搔き出しよく洗う。メスは子持ちなのでつぶさないように。尾ビレ以外のヒレをハサミで切って、ザルにあげ、ピンチに挟んで網をかけて翌日まで干す。加えて桶の蓋の周りに敷く縄を編むところまでが1日目の作業。
それぞれの選んだ鮒が混ざらないよう気をつけながら、皆で手分けして作業する。地元多賀の食文化を記録・情報発信しているYOBISHIの人たちは、作業しながら取材している。
いつも漬けている人は回を重ねるごとに工夫が増し、それぞれの細かいこだわりがあるようだ。様子を見に来た地元の名人は、鮒をピカピカに磨いて井戸水でよく洗うと話していたが、さらっと磨くのを好む人もいる。最初の洗い方からしていろいろあるとは思わず、初心者は丁寧に、とゴシゴシ磨いてしまった。
塩切り作業後には、塩漬け鮒が入っていた桶に魚醤が残る。ナンプラーより強烈な匂いにちょっと引いたが、持ち帰る人もいた。
2日目、いよいよ鮒に飯(炊いたご飯)を詰めて桶に漬け込む。3キロの鮒に2キロの飯を使う。飯は藤家の女将さんが前日早朝から用意してくださった。全部で20升以上の米を女将さんが一人で…すごい。米どころ近江ならではの郷土料理と実感。
桶にビニール袋2枚をそれぞれ丁寧に敷いてから、底に飯を一面に敷き込む。そこに、エラから口からパンパンに飯を詰めた鮒(オスの場合。メスは子を考慮して詰める)を並べていく。頭の向きは交互にとか、桶側の鮒は背があたるようにとか、並べ方にも細かな配慮。一面に並べたら、鮒同士がくっついて臭みが出ないよう、間に飯を挟んでいく。何だかいまいちの見た目な気がして、先生にちょこっと手直ししてもらったらとてもきれいになった。
その上にまた飯を敷き込み、鮒を並べていく。先生からは「いいですね!」とのお言葉。おいしく出来そう!という気になる。最後に蓋をするように飯を敷き詰めて、ビニール袋を丁寧に閉じる。これを持ち帰って、鮒と同量の重しをする。
帰宅後、重しを探す。庭から適当に石を見繕って体重計で測ろうとしたら、壊れて動かない。ご近所さんで測らせてもらうと3キロ弱、OK。鮒ずしを漬けたことがあるかと尋ねると、実家ではおじいさんやお父さんが漬けていたそうだ。嫁入り後の日夏では、業者が塩切鮒を持って漬けに来ていたとのこと。古道具担当が幼い時に祖父母と食べた、只々しょっぱい鮒ずしは多分それだったのだろう。「まぁ、がんばって」と励まされ、重しを乗せて桶を設置する。
置き場は雨や雪のかからない軒下、できれば朝日の当たるところがよいらしい。約1か月後、水が上がったら重しを増量、冬越しさせる。出来上がりはだいたい翌年の春からGW頃とのことである。
同じ場所で一緒に作っても出来上がった鮒ずしの味はみんな違うそうだ。本漬け作業からでも、鮒の洗い方や扱い、漬け方もそれぞれ微妙に異なるし、発酵食作り特有の、人の持つ菌、保存場所、お手入れなどいろんなことが作用する。ご一緒した人たちはほぼ地元の若い方たちだから、昔ながらの味も知っていて、なおかつ自分達なりのおいしさを求め、伝える実践をしているのだと思う。
古道具担当は「最初から上手く出来るはずがない」と全く期待していないが、果たしてどうか。作ってみてよかった!と思える鮒ずしになりますようにと願うばかりだ。それにしても、下準備や後片付けなどが大掛かりな郷土食作り。貴重な機会をふわっとくださった先生や、藤家のご夫婦に感謝します。

「宇曽川河口」 2024年 25×34cm
パネルに麻布、膠、油彩、オイルパステル、木炭など
鈴鹿山脈を水源として琵琶湖に注ぐ宇曽川。周辺には水田が広がる。
今住んでいる日夏村は、かつて宇曽川沿いにあった。
鉄道が出来るまでは水路として活用され、嫁入りも舟だったと聞く。
川﨑美智代 展「絵 鏡」
2024年9月14日(土)~9月20日(金)12:00~19:00 最終日は17時まで)
ギャラリーブリキ星 東京都杉並区西荻北5-9-11