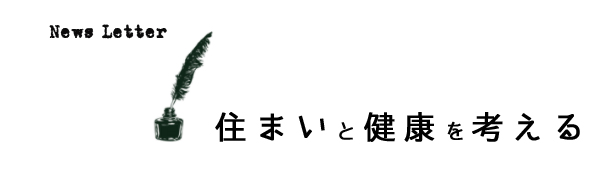フランスの室内空気質ガイドライン
5年前の2010年7月のトピックで紹介したことがありますが、その後さらに指針値が設定された物質が増えたので、改めて紹介します。
本内容は、5月中旬にオランダで開催された国際学会「Healthy Buildings Europe 2015」でフランス食品環境労働安全衛生庁(ANSES)が発表していました。
ただし、これらのガイドラインは、ANSESの勧告であり、フランスの正式なガイドラインではございません。日本と同様に審議会で検討されて正式なガイドラインとなっていきます。
1.ホルムアルデヒド(2007年専門委員会報告)
短期間曝露(2時間):50μg/m3
長期間曝露:10μg/m3
2.一酸化炭素(2007年専門委員会報告)
15分間曝露:100mg/m3
30分曝露:60mg/m3
1時間曝露:30mg/m3
15分曝露:10mg/m3
3.ベンゼン(2008年専門委員会報告)
長期間曝露:
・非発がん影響10μg/m3
・発がん影響2μg/m3(10万分の1のリスク)
・発がん影響0.2μg/m3(100万分の1のリスク)
中期間曝露(14日-1年、非発がん影響):20μg/m3
短期間曝露(1日-14日、非発がん影響):30μg/m3
4.ナフタレン(2009年専門委員会報告)
長期間曝露:10μg/m3
5.トリクロロエチレン(2009年専門委員会報告)
長期間曝露:
・発がん影響(10万分の1のリスク):20μg/m3
・発がん影響(100万分の1のリスク):2μg/m3
中期間曝露(平均15日の非発がん影響):800μg/m3
6.テトラクロロエチレン(2009年専門委員会報告)
長期間曝露:250μg/m3
短期間曝露(1日-14日):1380μg/m3
7.二酸化窒素(2013年専門委員会報告)
長期間曝露:20μg/m3
短期間曝露(1時間):200μg/m3
8.アクロレイン(2013年専門委員会報告)
長期間曝露:0.8μg/m3
短期間曝露(1時間):6.9μg/m3
9.アセトアルデヒド(2014年専門委員会報告)
長期間曝露:160μg/m3
短期間曝露(1時間):3000μg/m3