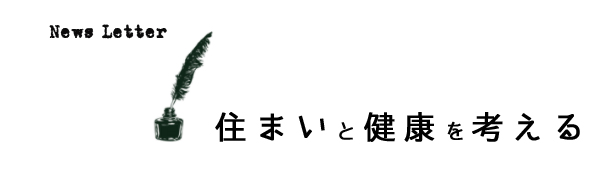平成25年度シックハウス関連の厚生労働科学研究報告
以下のサイトに、厚生労働省が主催した平成25年度生活衛生関係技術担当者研修会の報告資料が公開されています。
平成25年度生活衛生関係技術担当者研修会(平成26年3月5日)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/gijutukensyuukai/
これらのうち、ここでは以下の2つを紹介します。
1)建築物衛生の動向と課題及び環境衛生監視の実態
建築物衛生法に関連する空気環境基準等の実態や今後の課題が報告されています。以前にもトピックで紹介しましたが、事務所や学校用の建物で相対湿度と二酸化炭素の空気環境基準の不適合率がここ10年で上昇しています。
1つの原因として、個別空調設備が空調機の適用範囲に加わったことがあげられています。また、クールビズやウォームビズの温度の不適率原因の1つではないかと考えられています。個別空調設備のオフィスでは粒子状物質の濃度が中央方式のオフィスよりも高かったという結果も報告されており、空調機フィルタの捕集率の差が原因ではないかと考えられています。
その他、シックビルディング症候群関連症状と室内環境との関連では、粉じん濃度、アルデヒド類やトルエンの濃度、温湿度との関係が示唆されています。
2)室内空気環境実態調査の報告及び放射線問題の実態と対処法
全国500件規模の一般住宅における室内空気中化学物質を測定した結果が報告されています。そしてそのデータをリスク評価した結果、ベンゼン、二酸化窒素、ギ酸、塩化水素は、年間を通じてハイリスク傾向にあったこと、特にベンゼン、二酸化窒素、アセトアルデヒドは冬期にリスクが高い傾向にあり、生活習慣や燃焼型暖房器具からの排出物が関与している可能性が推定されることが報告されています。その他にも、化学物質に感受性が高いと考えられる人の全国調査などが報告されています。
上記以外では、レジオネラに関する最新の情報が報告されています。ご関心のある方は、この研修会で報告されたpdfファイルを上記のサイトでダウンロードできますので、ご参照ください。