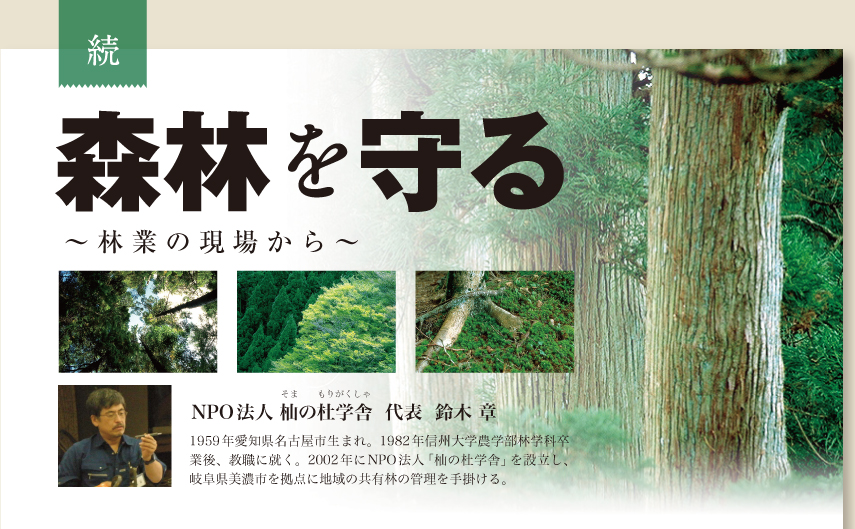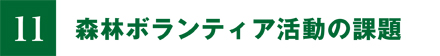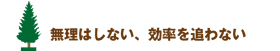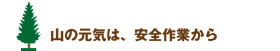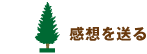昨年末、筆者の身近な地域で森林活動中の痛ましい事故が相次ぎました。一つは愛知県の高校の林業科で、生徒が伐採作業を参観者に見てもらう実習中、伐採したスギの木が参観者に直撃し死亡した事故。もう一つは岐阜県の公園内の森林で、間伐体験の説明を聞いていた小学1年の女児の頭に、折れて落下したスギの枝が直撃し死亡する事故が起きました。事故を検証してみれば、結果として森林作業における危険に対する認識の甘さや、安全対策の不備が指摘されることになると思います。森林ボランティア活動や一般市民の森林作業への参加に積極的に関わる筆者も、森林作業が人命に関わる危険と背中合わせの環境にあることを改めて認識し、切実な問題として考えなければならないことが多くあります。
筆者は、森林ボランティアや森林の所有者の方々を対象とした講習会に講師として呼ばれることが多くあります。一口に森林ボランティア活動と言ってもさまざまな活動があり、その中でも人工林の間伐ボランティアという活動では、木を伐るという危険行為と、混み過ぎた人工林を間伐で再生するという活動目的をどう折り合いをつけていくかが課題となってきています。活動に参加されている方々の多くは森林に対する意識や関心も高いし、伐木の技術に関しても向上心が旺盛で感心させられます。しかし、最初は恐る恐る小さな木を伐っていた人も、腕を上げればチェンソーで大きな木も伐れるようになる。それと同時に危険要素も増えてくるのですが、多くの人がもっと太くて大きな木を伐りたいという欲求にかられていきます。間伐で手入れ不足の人工林を再生するという当初の目的から、倒すのが難しい木を伐ることが目的に変わって本末転倒な事態に陥ってしまうケースも出てきています。しかし、森林作業では、一度事故になれば自分や他人の命を奪う深刻な事態になることをしっかりと認識する必要があるのです。

岐阜県恵那市で開催した 「山仕事手習い塾」の様子(2013/1/19~20 開催)
職業としての林業の現場作業は決して楽なものではありません。林業現場の安全管理やリスク管理の近代化も進められてはいますが、山や木は自然の産物であり規格化やマニュアル化が難しく安全管理も難しいのが実情で、残念ながら林業現場での怪我や事故が多いことも事実です。筆者の周りの多くの仲間も怪我や事故が原因で林業現場を去っていきました。林業の現場で働いている人達は、森林という自然を相手に働く心地よさと同時に、木を伐るという作業が大きな怪我や命にかかわることを身をもって知っています。
それに対して、森林ボランティアの方々は圧倒的に経験時間が短く、経験時間に対して頭からの知識のほうが先行してしまいます。その結果として行為に対する危険認識が甘いことが多々あるのです。職業として林業に従事する者は、作業の効率と作業の安全の狭間の中で折り合いをつけながら作業せざるをえないことも現実にあります。しかし、作業の効率を追わないボランティア活動や所有する山林の手入れでは、最も安全な方法で一本一本を丁寧に作業することが最善策ですし、難しい作業は無理せず専門家に頼めばいいわけです。自分や仲間が怪我や事故にあえば楽しくないし活動も続きません。
私たちが行っている講習会では、本来の目的であるスギやヒノキの人工林を適切に管理するための考え方と、それを実現するための安全作業の基本を身につけていただくことを主眼に講習のプログラムを立てています。それは、先人の努力によって植林された人工林を地域の財産として見直し、適切に管理していくことが必要であると考えているからです。そういう意味からも、素人の方でも基本さえ身につければ、安全に間伐作業のような森林作業ができるようになり、ボランティアの方々や地域の人々が地域の山に入り、地域の山が元気になっていくことは素晴らしいことです。この活動の原点を見失わないように、今後も講習会などを通じて地域の森づくり活動を地域の皆さんと一緒になって考えていきたいと思います。

まずは、座学で勉強。

「どの木を残して、どの木を伐るか。」

安全な伐木技術の基礎をしっかりと 身につけることが、怪我から身を 守る近道