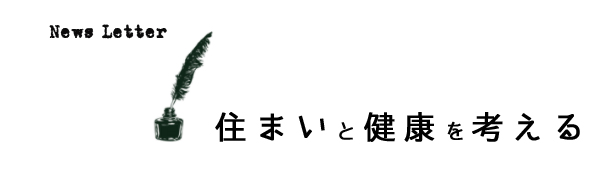米国環境保護庁の4カ年戦略計画
米国環境保護庁は、2014年から2018年までの4カ年戦略計画において、以下の5つを戦略目標と位置付けました。
1)気候変動への取り組みおよび空気質の改善
2)国内の水域の保護
3)地域社会の浄化と持続可能な開発の推進
4)化学物質の安全性の確保および汚染の防止
5)法の執行と遵守の確保による人々の健康と環境の保護
米国では、日本と異なり、環境保護庁が室内環境を所掌しています。室内環境に関係するところは、1)空気質の改善です。空気質の改善では、健康や生活保護に基づいた空気汚染の基準の達成と、有害な空気汚染物質や室内空気汚染物質による健康リスクを削減することが戦略目標となっています。
米国では2003年から2011年にかけて、PM2.5とオゾンの大気汚染濃度はそれぞれ26%及び16%減少しました。しかしながら、2010年時点でも、いずれかの物質の環境基準を越えている地域が約40%残っています。大気汚染物質によっては、長期間曝露すると、発がん、短命、免疫・神経・生殖機能の傷害、循環器や呼吸器の障害のリスクが増加する可能性があります。
室内空気では、室内のアレルゲンや刺激物質が喘息の増悪に大きく関わっていると報告しています。米国では2010年において2600万人が喘息に罹患しており、約200万人が救急外来を受診しています。また、2008年では、喘息患者のうち、半数以上の小児、3分の1以上の成人が、喘息が原因で学校や職場を休んでいます。
日本では問題が少ないと考えられていますが、米国では室内のラドンによる肺がんで毎年約2万1千人が死亡していると推算されています。
また、人口の約20%に相当する人々が小中学校の屋内で日中過ごしていますが、屋根の水漏れや空調・換気装置の問題などで、喘息やアレルギー疾患を引き起こす可能性があると指摘しています。
喘息に関連する室内空気汚染の問題については、以下の戦略を掲げています。
2018年までに、家庭や学校で喘息に関連する室内汚染物質への曝露を削減し、そのような対策が実施された人の数を2003年の3百万人から9百万人と3倍に増加する。特に、人種や民族間の不均衡の是正を重点化すると報告しています。
Read More