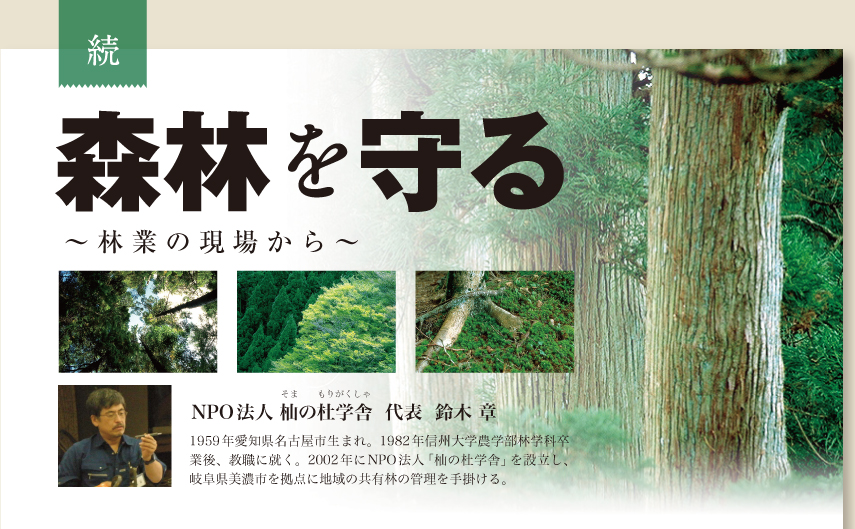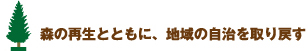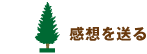去る5月25日~27日までの3日間、岐阜県恵那市中野方町に全国から80数余名の参加者が集まり、第1回「木の駅サミット」が開催されました。2009年にこの中野方町で始まった「木の駅プロジェクト」も、鳥取県智頭町、愛知県豊田市・新城市、岐阜県大垣市、高知県土佐町で立ち上がり、更なる広がりを見せています。詳しくは「木の駅プロジェクトポータルサイト」を参照してみてください。

岐阜県恵那市で開催された「第1回木の駅サミット」
この疑問に「木の駅プロジェクト」の推進者である丹羽健司氏(vol.4に前出)はこう答える。「『道の駅』に大根を出すでしょう。あんなふうに、2mより短い木でも軽トラに乗せて『木の駅』に出せばお小遣いになるんだよ」と。高知県のNPO「土佐の森・救援隊」がはじめた間伐材と地域通貨(※1)の交換システムは、「C材(※2)で晩酌を!」を合言葉に、森林所有者や森林ボランティアの方々が気軽に木材を搬出して収益を得ることを可能にしました。このシステムを全国どこでも導入できるように標準化し、地域に定着させる取り組みが「木の駅プロジェクト」と呼ばれる各地の取り組みです。
※2 形質が悪く市場価値の低い丸太。搬出されずに林地に放置されることが多い。
筆者は「木の駅プロジェクト」の活動に、間伐作業の安全講習のお手伝いでかかわらせていただいています。「木の駅」の取り組みは、森林所有者や森林ボランティアの方々が「間伐材を搬出して収益を得る」という行為を容易にし、森林資源の活用に直接的にかかわることができるようにした画期的な取り組みです。中山間地にとって森林は大切な地域財産であり、誰もが今の放置された人工林の現状を「良し」とは思っていない。きっかけさえあれば、自分達でなんとかしたいと思っている仲間はたくさんいる。森林作業も基本を身につければ結構楽しいし、地域の山の財で得た収入で晩酌ができるならこんないいことはない。こんなことを地域で話し合う場をつくるところから「木の駅」の取り組みは始まります。この地域の人達の気持ちを形に変えることが、地域で森林を守り、地域の自治と誇りを再生していくことにつながるのだと思います。
利用されずにいた間伐材が地域通貨と交換され、地域の資源が地域通貨となって地域内で循環する。地域通貨は「木の駅」の取り組みが地域の経済やコミュニティーの活性化に貢献する重要なツールであることには違いありません。
しかし、現状では間伐材と地域通貨の交換には、多くの「木の駅」実施地域で外部資金を投入して成立させています。それは「木の駅」で搬出されるチップ用の丸太の市場価値はトン当たり3,000円程度で、この価格では搬出の労力を考えると市場が回りにくいためです。そのために買取り価格に外部資金を上乗せして、トンあたり6,000円程度で間伐材の買取りをしています。「木の駅プロジェクト」の導入時は、この上乗せ分の資金を行政やNPOなどが補助金や助成金等を使って負担していることが多いのです。公的補助金を投入して、林業と地域の再生の効果を上げることも行政参加のひとつの考え方ではありますが、「木の駅」を恒常的に地域に定着させるには、資金の独立性も今後の課題になってくると思います。
前述のように「木の駅」取り組みは、森林所有者や森林ボランティアの方々が市場に間伐材を出荷する受け皿をつくり、なおかつ、その活動が地域のコミュニティーの再構築につながっていることに大きな意義があります。
最近、この「木の駅」の活動に行政も大きな関心を寄せています。しかし、一方で「木の駅」の取り組みやvol.4で紹介した「森の健康診断」の活動は、いい意味での「地域活動」や「市民活動」であってほしいという願いもあります。行政機関は、日本の森林・林業の「根幹」の部分の政策をしっかり進めていただきたいと思いますし、それだけではカバーできない「枝葉」の部分は「木の駅」や「森の健康診断」の地域活動や市民活動でフォローすれば良いと思っています。地域再生や林業再生の名のもとで、行政に「地域力」や「市民力」をコントロールされるのは面白くありませんし、安易に公的資金を頼ることはむしろ「地域力」や「市民力」の損失を招くと思うからです。
今後の「木の駅」の取り組みの中では間伐材を薪などに加工して付加価値をつけるなど、さまざまなアイデアで、独立採算で「木の駅」を回す取り組みも考えられています。各地域の実情に合わせた「木の駅」の進化に注目してみたいと思います。