日本のフレスコ画は余り知られていないが、フランク・ロイド・ライトの建築で有名な東京西池袋の自由学園 明日館で昭和6年、生徒達によって描かれたフレスコ画がホールの西壁の漆喰の上塗りの下から出て来た。日本での本格的なフレスコ画は、特に戦前のものは数少ない。国の重要文化財である建物とともに一見の価値がある。
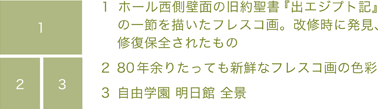
- Q フレスコ画はどのような方法を用いてつくられるものなのでしょうか?
- 壁画には塗った壁の生乾きの間に絵を描くものと乾いて固まった壁面に絵具などで絵を描くものとの2つの方法があり、フレスコ画は水で絞っただけの顔料で生乾きの漆喰壁に絵を描くものである。それゆえに、彩画の時期があって一日一日時間をかけて仕上げることになる。
- Q 日本でも壁画はありますか?
- 日本の壁画は古墳の内部や法隆寺の寺院建築にみられるだけで、障壁画やふすま絵が主流である。壁画に似たものとしては、土蔵建築などがさかんになった江戸時代以降の漆喰鏝絵があるだけである。ヨーロッパは石や煉瓦による壁構造ゆえに、フレスコ画等の壁画が描かれた。日本では明治以降洋風建築が入ってきたが、日本画の伝統が根強く、壁画に導入されなかったといってよい。
■フレスコ画とは
フレスコ画のフレスコという言葉はイタリア語で“新鮮”という意味を持ち、フレスコ画の色がいつまでも褪せず、新鮮であるためフレスコ画といわれるようになった。フレスコ画は、西洋の漆喰(砂と石灰)を塗り、その漆喰が生乾きの内に、水で溶いた顔料で絵を描いたものをいう。石灰が炭酸ガスを吸って固まり始め、乾き、絵を描くことで顔料も一緒に石灰石化することで、新鮮なまま残る。フレスコ画はヨーロッパの壁画として教会等の内壁や天井に描かれ、ルネッサンス絵画の主流になった。
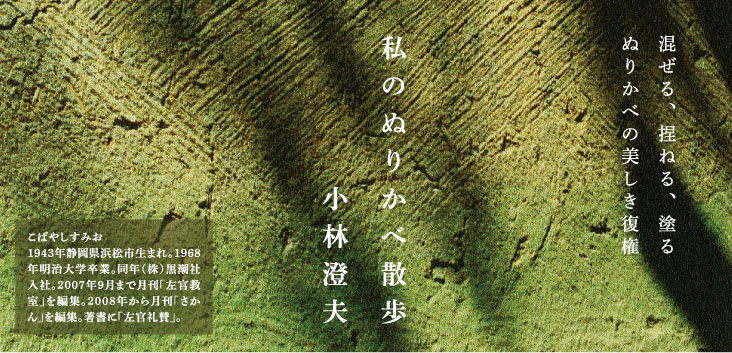
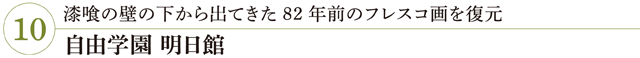
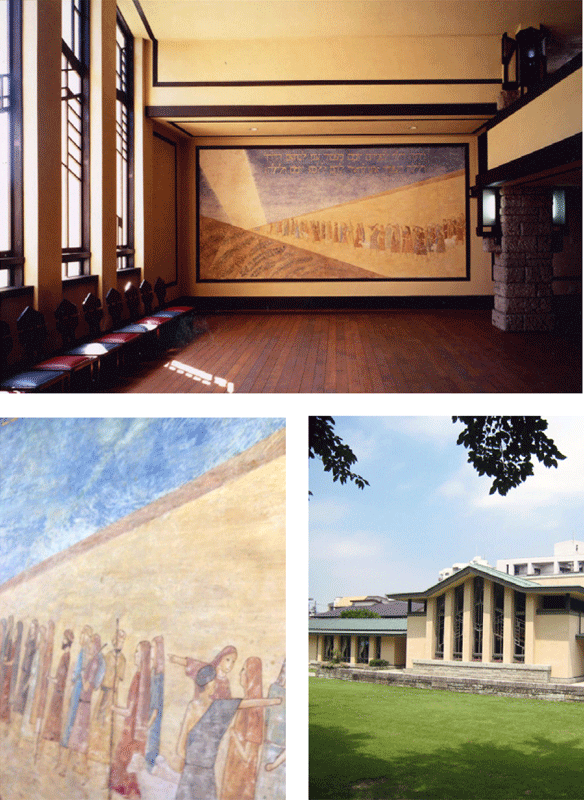


![[左]2000年余りたっても色彩鮮やかな人物像のフレスコ画[右]ポンペイに保存された植物を描いたフラスコ画 [左]2000年余りたっても色彩鮮やかな人物像のフレスコ画[右]ポンペイに保存された植物を描いたフラスコ画](/column/nurikabe/wp-content/uploads/2013/09/02.png)