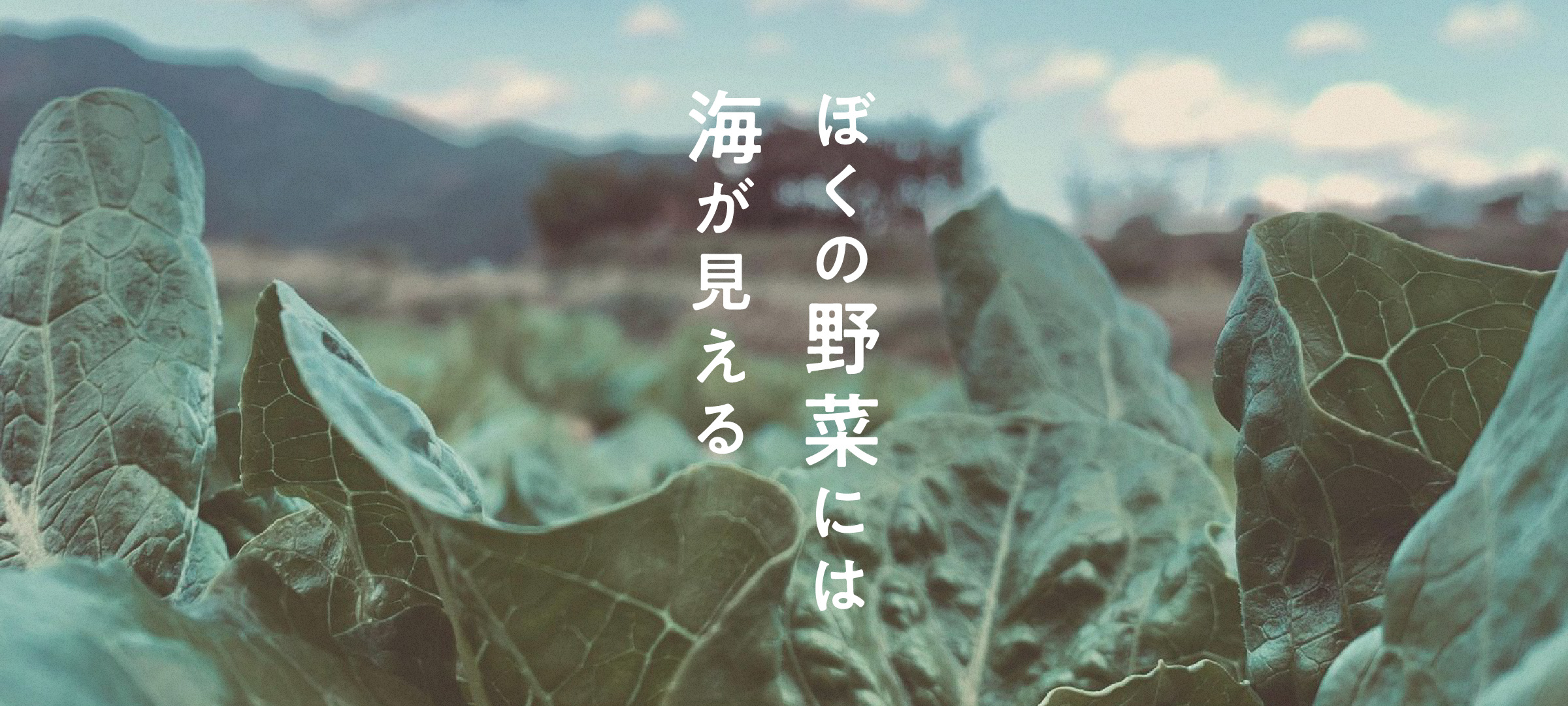酒井抱一の「夏秋草図屏風」は、ぼくが最も好きな画の一つだ。
この図屏風は尾形光琳の「風神雷神図」にインスパイアされて、裏面に制作されたという。金箔に描かれた闊達で、力強く躍動感に溢れた風神雷神の豪放磊落な図象とは対照的に、銀箔の背景に余白を十分にとり曲線を際立たせ、どこか翻弄されるように描かれた静かだけれども豊かな植物群と群青色の水。学生の頃は、この二つの画の縁由を、動と静、陽と陰みたいな対比でしか鑑賞できなかった。
就農して直後のことだ。突然の豪雨に遭い、軽トラックに逃げ込んでしばらく田んぼを眺めていた。稲の育ちが芳しくなかった。周りの田んぼに比べ葉色が薄すぎる。ぼくは、追肥をすべきか否か午前中考え込んだ。途中、草刈りを挟んだら15時を回っていた。ふと濃い雨の匂いがした。東側に気を向けると比叡山の方から空気が引っ張られるように西側の山の稜線方向に向かって強い風が巻き起こった。一瞬、気温が下がり今まで鳴いていたニイニイゼミの声が止む。

遠くから地響きの如く雷鳴が轟く。大原の西、花背の方を見ると薄墨を何層も重ねたような雲の中に雷光が激しく見えた。圃場のあるウエンダから3キロ先の向かいの金毘羅山はすでに雨で霞んでいる。やがて再び塊のような強風に煽られて、大粒の雨が軽トラックのフロントガラスにボタッと落ちて、大きく音を立てるや否やワイパーの動作が無意味なほどの豪雨となり、空気が裂けんばかりの雷鳴を立て続けに落としながら、その分厚い薄墨色の雲は頭上を通過した。まさに風神雷神とはこのことで、畏怖を感じる迫力と緊張感だった。
雷雲は琵琶湖に抜けた。比叡山の方から陽が差し込み、それをいち早く察したニイニイゼミがまた鳴きだす。蒸し暑さがより増した。

それからしばらくすると、さっきまで薄い緑だった稲が、血色を取り戻したかのように色を上げ、背丈が伸び葉のしなりが力強くなっている…… 空気中の窒素を固定するためには巨大な電力がいるというのはどこかで知っていた。けれど、自然の大きな力を感じたのはこの時が初めてだった。

稲は雷で実る。稲にとって伴侶のような存在だから「稲妻」。初めて聞いた時は、「ホンマかいな」と思ったが、嘘じゃない。雷の放電で空気中の窒素と酸素がイオン化され窒素酸化物として雨に溶ける。稲の養分として大地に降り注ぐ。

虫の動きや太陽の傾き加減で色調を変える葉の色から、野菜や稲の健康状態を日々観察する。微妙な変化にも反応できるようになり、同時に自然から享受する驚きも増えた。一日の大半は、こんな感じで過ごす今のぼくには、光琳に応えた抱一のこの図屏風が、いとも巧みに自然の摂理を図象化した、とてつもなく壮大な画で、豊穣のアイコンにさえ思える。この画が目に触れるだけで、そんな農家としての自分が誇らしく感じるのだ。ぼくは、光琳と抱一の眼に少しでも近づけたのだろうか。