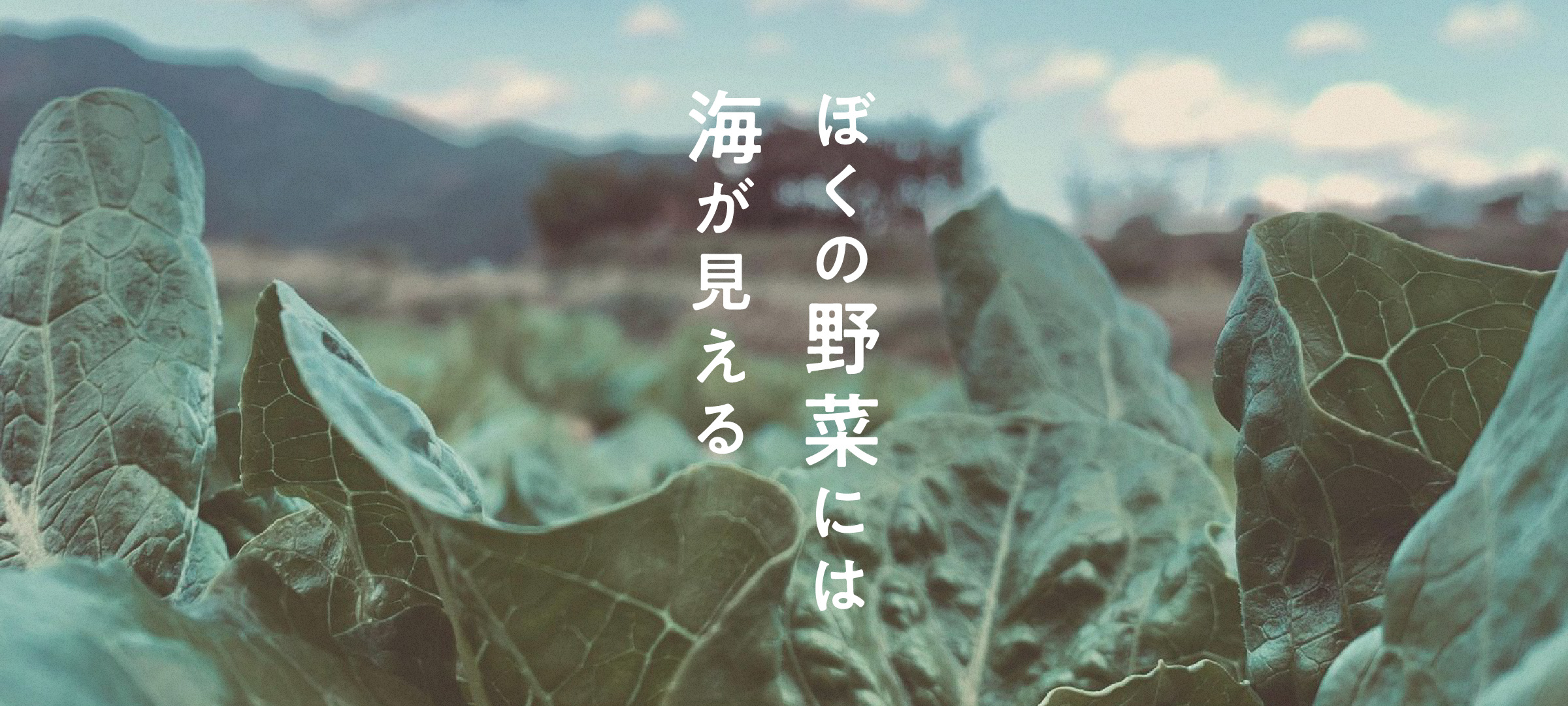梅雨の季節の楽しみは、セロリの香りと冷えた吟醸酒をペアリングすること。これが病みつきになる。ほのかな日本酒の果実香とセロリの香味が、疲れた身体をフワッと癒してくれる。穀物由来とは思えない日本酒の華やかな香りは、選りすぐられて培養されてきた酵母の仕業だ。酵母は低温で飢餓状態になると香気成分を放つ。その性質を利用し、酵母が活性を失わないギリギリの低温でゆっくりじっくり発酵させる。ここが杜氏の腕の見せ所だ。酵母にストレスをあたえて、人間の嗜好に添ったものをつくりだすのは、日本酒だけに限ったことではない。ぼくらが栽培する冬野菜にも通じている。
毎年、10月の頭に冷気の溜まる場所を選んで鞍馬大根のタネを蒔く。ぼくの大根は宅配先のお客さんの中では「梨みたいな大根」と呼ばれていて、冬の楽しみにされている人も多い。大根は厳冬期を迎えると寒さから凍るのを防ぐために糖度を蓄える。だから、水はけの非常に良いウエンダの畑地という特性に加え、寒さに耐えうるよう代謝を強めるイメージで肥料を配合した土を作り込む。さらに糖度を極限まで引き出すために冷気の流れを常に読み、あとは寒気を待つ。冬野菜はこんなふうにストレスを与えながら栽培するが、天候を見誤ると一晩で凍って全てが台無しになってしまう。
一方、夏野菜はストレスを与えない方が野菜の味が良い。キャベツも虫がつき過ぎるとなんだか辛みが増すような気がするし、今がまさに旬のズッキーニも、セオリー通りに下葉を掻きすぎると病気のリスクが高くなるばかりか樹勢が弱くなって収量が落ちる。万願寺とうがらしも然り。基本的には初期の手入れが肝心で幹を頑丈に仕上げたら、あとは葉色と実の付きを観察し徹底的に病気が蔓延するリスクから遠ざける処置を適宜する。あとは夏の日差しを待って日光と水分を欲しい分、欲しいだけあげて伸び伸びと栽培する。その方が、素直に美味しい。一年を通じて季節それぞれの栽培と発酵の技があるけれど、いずれにせよ自然の環境をできるだけ読み解きながら植物の特性と合わせ、じっくり成長を見守ることが美味しい野菜を作る肝なのかもしれない。
去年の夏の終わりから、宅配先の家族の子の大学生が手伝いに来てくれている。今年、4回生の彼は農業で身をたてたいと決意した。当初から農に関心あるだけあって、ぼくの農園に来た時から物覚えがよく体力も申し分ない。夏野菜のように育てるべきか? 冬野菜のように育てるべきか? なんてついつい接し方を考えてしまうが、小学校に行きたがらない長男をコントロールしようとして毎回手を焼く自分の姿を思い出して苦笑してしまう。少しばかり野菜の栽培ができるようになったからといって、それを人の育て方にまで応用するなんておこがましい。来年、しっかりした農家にお世話になることになる彼には、これから始まる農業の喜びや苦労、葛藤はまだまだ先の話。今は見守る時期だ。
「じっくり待つことを知らない人間は、いい酒つくれないし、米も野菜もいまひとつなんだな」こんなことを言っていたのは、今、セロリをアテに飲んでいる吟醸酒を造った、ぼくが尊敬する秋田の酒造り名人だ。夏場は芹栽培の名人でもあるその山内杜氏は、人を育てる名人でもある。