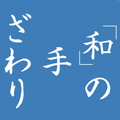座布団

古代、身分の高い人々が寝具として使っていた「筵(むしろ)」という一畳分ぐらいの敷物が進化して、藁や綿を詰めた「褥(しとね)」が、座布団の原型と言われています。
日本では鎌倉時代のはじめ頃、中国に渡っていた臨済宗の開祖の栄西や曹洞宗の開祖である道元が、禅の文化と同時に、懐石料理や御座布団の文化を日本に持ち帰ったのが始まりとされます。円形は天空を表すので神仏に仕えるお寺に、四角は地上を表すので天皇に、と形にも意味が込められ、権力の象徴を表す道具として用いられてきました。1700年頃には、当時文化と教養の発信地としてサロンや料亭のような役割を持っていた遊郭で用いられるようになり、その後、明治から大正にかけて、漸く一般庶民の手にも届くようになりました。
正方形のように見えるけれど、じつは縦横の長さが微妙に違うこと。四角の房は綿がずれないようにというばかりでなく、邪気を祓う意味も持っていること。中央に施されている三方の綴じ目が、座布団の前後を決めていること。上部が膨らんだ形によって、体重を逃しやすくしていること……座布団にまつわる歴史と文化、そして、綴じ方や形状に込められた深い意味を詳しく教えてくださったのは、明治から続く寝具屋の五代目、「手作り京座布団プラッツ」代表取締役の加藤就一さん。
店内には、銘仙判や八端判など定番もの、京都ならではの寺社用のもの、デスクワークやお昼寝用と多様な商品が並びます。素材や形の組み合わせも自由で、自分用にも贈り物にも人気だそう。試作品は必ず自分で第一号を作り、職人やお客様から様々な意見を聞いて取り入れること、と職人気質の一方、海外出張にも精力的に飛び回る加藤さん。外国からの客人も多い嵐山の地で、京都人を演じることも、また文化を守り広めるために必要なこと。という一言に、強い誇りとものづくりへの愛情が感じられました。
西陣織小座布団 5,500円(税抜)
株式会社プラッツ
〒616-8384 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町5
H P:http://www.kyoto-platz.jp/