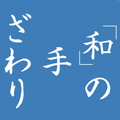つげ櫛

黄楊(つげ)の木が櫛に使われるようになったのは奈良時代。 「ぬばたまの わが黒髪を 引きぬらし 乱れてさらに 恋ひわたるかも」「君なくは 何ぞ身装はむ 櫛げなる 黄楊の小櫛も とらむとも思はず」・・・『万葉集』にも数々詠まれているように、艶やかで真っ直ぐな美しい黒髪は古来日本の女性美の象徴であり、その美しさを保つための大切な道具として「つげ櫛」の存在がありました。江戸時代以降は身分によって髪型が異なり、髪飾りなどの装飾品にも使われるようになったため、さまざまな形が生み出されましたが、その製法は現代にいたるまでほとんど変わっていません。
「うちでは、鹿児島県指宿産の黄楊をつかっています。堅くて粘り気があり、櫛づくりにとても適しているのです。ひずみの少ない丈夫な櫛にするために樹齢30年ほどの木を探し、燻し、10年程乾燥させてから加工します。髪通りのよいきめ細やかな櫛をつくるために、奈良時代から変わらない職人の丹精な手仕事で、一つひとつ木目を見ながら丁寧に仕上げます」と語る、明治8年創業「十三や」五代目の竹内伸一さん。「つげ櫛は使用するにつれて歯の部分が削れ、使っている人の髪質に合ったものになっていきます。天然木なので静電気も起こりにくく、髪を傷めることなくお手入れできます。一か月に一度、椿油に一晩か二晩浸けてお手入れすれば艶やかさが増し、汚れもつきにくく髪通りもよくなって、20年30年と長く使っていただけます」
使うほどに美しい飴色になり、自分だけの形に育っていくつげ櫛。今も昔も、美しくありたいと願う女性たちから、変わらずに愛されて続けています。
写真上 つげ4.5寸とき櫛 11,500円(税込)
ちりめんケース 1,050円(税込)
写真下 つげ手彫(梅)荒とき櫛 14,700円(税込)
十三や
〒600-8003 京都市下京区四条通寺町東入13
TEL:075-211-0498
営業時間11:00~20:30