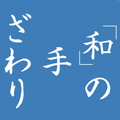南部鉄器

江戸時代初期、南部藩(現在の岩手県一帯)の領主が茶釜づくりを保護育成し、多くの鋳造鉄器がつくられました。その製法は現在まで継承され、南部鉄器と呼ばれています。盛岡市紺屋町の「釜定」は、明治後期に創業した南部鉄器の老舗。戦後、創業当時の図面から再建した現在の店舗は、天井に太い梁がかかり、間口が狭く奥行きが深い、昔ながらの商家のつくりです。
錆びが心配される鉄製品ですが、釜定では錆びのクレームは一度もないとのこと。そのわけは、南部鉄器独特の「金気止め」を施すことにあります。鉄器は鋳造された後、炭火の中で熱され、表面に黒錆びという薄い膜をつくります。この錆が新たな錆を防ぐのです。また、原料の銑は錆びにくく丈夫になるように、成分調整されています。これらの作業には化学的な知識と共に、経験が必要となります。「手仕事とはどんどん引き込まれていくもの」と話す三代目の宮伸穂さん。長い伝統の中で、より深い造形と良質な鉄を求め、宮さんの創作世界は広がります。
宮さんが「洋鍋」をデザインしたのは30年ほど前。南部鉄器の良さを新しい形で生かせないかと、家業の鉄瓶づくりなどのかたわら、考案。持ち手の木には檜を使用。取り外しができるので、オーブンでも使えます。鋳物は保温性が高く、油との相性もよいので、深さのある洋鍋は煮る・焼く・揚げると、一つの鍋で多様に対応可能。南部鉄器の伝統が生んだシンプルで実用的な鍋です。
洋鍋は(小)5,040円、(中)9,450円、(大)13,125円

鳥のオーナメント 4,725円
釜定
〒020-0885 岩手県盛岡市紺屋町2-5
TEL :019-622-3911
※下記のお店でも取り扱っています。
designshop