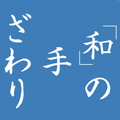扇子
ウォークマンしかり、コンパクトに精巧につくるのが日本のお家芸なら、扇子はその元祖といえる発明品かもしれません。工程をごく大雑把に追うと、まず和紙を5枚又は、7枚ほど張り合わせた下紙に絵付けをし、真ん中の和紙にヘラを差しこんで二つに裂き、骨を通す入り口をつくる。地紙を湿らせてから二枚の折り型紙の間に地紙をはさみ地紙を折っていく。先述の入り口から竹の棒を通して「骨の道」をつくったら、一度ぐっと締めて形を整え、天地を切る。最後に、口で吹いてパカッと開いた「道」に、糊をつけた骨を差しこんで両わきの親骨を熱してうち側にまげる。
「このパチンと閉じるところが日本の美学なんだね。だから骨には必ず、しなりのある竹を使います」と話すのは、浅草・文扇堂の四代目主人、荒井修さん。分業制が一般的な扇子の世界で、荒井さんはまず大学時代に仕立ての修業に入り、それから絵付けを独学で習得。歌舞伎役者や噺家などから、オリジナルのデザインを任されることもしばしばです。
「たとえば緋色の地に牡丹を描くなら、色は実際に見せたい色より一杯薄く、牡丹は少し横に広げて描きます」。これは、色は折り山の影で濃く見え、柄は山が寄って縦長に見えるから。また、絵付けは日本画と同じく鉱物などの顔料を膠で溶いて使いますが、膠が濃いと折り山に割れが入ってしまうので、厚塗りは禁物。立体ゆえに、そんなところは日本画より難しいといっていいでしょう。
写真の扇子は、地元浅草の三社祭の時期につくる「網」。懐に忍ばせれば、いよいよ夏がやってきます。
5月の三社祭の時期に売り出される「持ち扇 網」は、同じ絵柄で男持ちと女持ちがある。
男持ち・白竹、女持ち・塗り骨 黒は各種税込8,200円。
※受注後に製作するので、受け渡しまでは少し時間がかかります。
文扇堂 雷門店
〒111-0032 東京都台東区浅草1-20-2
TEL/FAX :03-3841-0088
※仲見世店もあり