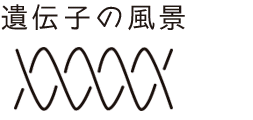私が中嶋夏の舞踏を初めて観たのは、フランスのナンシーで開かれた演劇フェスティバルでした。
金沢美術工芸大学の交換留学生としてナンシーに滞在していた 私は、日本から演劇が来るという噂を聞きつけて、迷わずチケットを手に入れたのです。
「庭」とだけ書かれた小さな白い紙片には、顔のような絵が印刷されており
それを手に私は一人で劇場に向いました。
その頃(1983年当時)の私は、「暗黒舞踏(BUTOH)」という言葉さえ知りませんでした。
日本ではテント芝居や演劇には親しんでいましたが、舞踏という表現にはまだ触れたことがなかったのです。 1984年6月のその日、ナンシーの劇場は満席でした。
幕が上がった瞬間のことを、私はいまでもはっきり覚えています。
音楽があったのか、なかったのか。
あったとしても、おそらくかすかな音だったのでしょう。
何よりも、私の視線はある一点に釘づけになっていました。
袖の暗がりから、白い衣装をまとった「存在」が現れる。
人というより、むしろ彫刻のような、あるいはこの世のものではない影のような。 両手には大きな植物の束を抱えており、動きは遅く、照明の薄暗さのせいか前に進んでいるのか、後ずさりしているのか、判別がつかないほど。
顔や首、手足は白く塗られていた。目を閉じ、口元はかたく結ばれている。
ときおり、その表情に苦悶のような陰が走るのです。
舞台の中央に辿り着いたその人が、その後どのように動いたのか。
記憶はあやふやだけれど、その時間、私はあきらかに「今まで見たことのないもの」を見ていました。 圧倒され、困惑し、驚き、夢中で、その終わりまで目を離すことができませんでした。
終演後、観客は一斉に立ち上がり、拍手が鳴り止みませんでした。
あの出会い以来、私は暗黒舞踏というものに強く惹かれていったように思います。
当時の私はまだ二十二歳。
何も知らない、ただの子どもでした。
美大の学生として、私がしていたことといえば、キャンバスの前に座り、絵の具を塗りたくる、紙に色を塗り、それを切って組み合わせて立体をつくる、その程度のことでした。
限られた「アート」というくくりの中で表現することと、肉体を用いた舞踏の在り方は、あまりにも違うように思えて、自分が立っている場所がはじめから敗北を予感させるような場所に思えました。まだ何も始まっていないのに、どこかで負けてしまっている——そんな感覚が、胸の奥に湧き上がって何か苦しさを覚えました。
美術の枠で考えることには何か重圧があって、その重みを、若い私はまだ受け止めきれず、自分が考えているようなことなど、世界ではもう誰かがとっくに考えつくしていると悟りました。
少なくとも、当時の世界では、舞踏はまだその価値が定まっていなかったように思います。中嶋夏の舞台も、ヨーロッパの観客にとっては未知のものであり、驚きをもって迎えられていました。舞踏は、前衛の中でもさらに先端に位置していたのです。
そしてそれは、若い私の目にも、明らかに視覚芸術としての価値の高さを感じさせるものでした。

中嶋夏 金沢公園 《夢の夢 奥の奥 残りの火》2022年 photo 2枚共 : Nik van der Giesen
当時はまだインターネットもなく、フランスで舞踏について調べる手段はありませんでした。それでも私は、興奮の余韻に身を任せたまま、毎日の課題に追われるように日々を過ごしており、拙いフランス語でレポートを書き、制作に向き合いながら助成金だけを頼りに、わずかな仕送りで暮らす苦学生としての一年でした。
ナンシーはパリから東へおよそ390キロ、アルザス地方の西端に位置する街で、アール・ヌーヴォー発祥の地とも呼ばれています。
エミール・ガレを中心としたナンシー派の美術館が街の誇りだった。
今ではTGVでわずか2時間半の距離だと聞くが、当時の移動には、確か四時間ほどかかったと記憶してます。
ナンシーでの学生生活については次号へ
続く