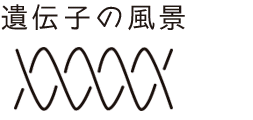2025年4月5日、東京に出向いた。昨年メキシコでの公演後に倒れ、あの世に行ってしまった舞踏家中嶋夏を偲ぶ会のために出かけたのであった。
夏さんについては次回の遺伝子の風景に詳しく書いて行こうと思う。
はじめて東京に行ったのはいくつの時だっただろう。日本に「とうきょう」、という場所があり、大都会で華やかな人たちがいて、スターたちがいる。その場所にある種の憧れを抱いたのは小学生のころだったかも知れない。
当時、金沢から東京へ行くには、特急に乗っても8時間ほどかかった。電車の窓は上に自分たちで押し上げる形だったように記憶している。窓側に小さな台?がついていて、そこにプラスティックの蓋つきの容器にはいった番茶を置いて、時には凍ったみかんを、売店で買って旅のお伴にするのだった。

アーティゾン美術館で開催中の「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ 」より、ゾフィー・トイバー作品
東京に初めて行ったのは母とだったと思う。東京、というのは母にとって「銀座」を意味していたのだろう。とりわけ、銀座4丁目の「ちとせや」という店であんみつを食べたい、というのが母の口癖だった。当時の電車は上野に到着。新橋、銀座、赤坂、澁谷、新宿、駅名どれを見ても、聞いたことのある、テレビやラジオに出てくる地名ばかり。
当時は多分7歳くらいだった自分が、銀座4丁目の交差点を母に手をつながれて渡った記憶がぼんやりと蘇る。
さて、「ちとせや」で、甘いものやで検索しても全く出てこない。もしかしたら母は千疋屋のことを「ちとせや」と呼んでいたのではないだろうか。 1894年(明治27年) 新橋(銀座)に千疋屋オープンとある。
横浜生まれの母は金沢の父と結婚する前に、東京は銀座の料理屋(?)の息子と結婚していた。その人とは子どもができなかった。そのためかうまくいかず、数年で別れ北陸に出戻った。以前から母のことを思い続けていた父と再婚する。
母にとって銀座はお上りさんが憧れて行く場所ではなくて、苦い切ない思いを携えて行く場所だったのだ。複雑な気持ちを抱えた母の心情はいかばかりだったか。もちろん、小学生の私はそんなことを知る由もない。
私が一人で東京に行くようになったのは美術大学時代だと記憶する。美大の小娘の目的は、東京で展覧会を見ることだった。昭和50年代末はインターネットは当然ないから、美術手帳、芸術新潮など美術雑誌から得た貴重な情報を辿って、金沢から普通列車で夜に出発する。もちろん当時はお金もない。寝台列車ではなく2人ずつの固い椅子が向い合せの席に座っていく。知らないお兄さんがお向かいの席で新聞を読んでいた。よく見るとそのお兄さんの両手の小指の先が無かった。目を合わせないようにしながら、ドキドキしながら朝まで列車の中で過ごした。あれから幾度となく東京へ行っているが、時々はじめての東京を思い出して、不思議な気持ちに包まれる。
中島夏を偲ぶ会は夏さんが霧笛舎のメンバーと練習場所としてつかっていた四谷ひろば、という旧小学校のスペースで行われた。彼女の汗と涙がしみ込んだ場所に私は深い感慨とともに立っていた。樺太生まれの夏さんが両親とともに汽船に乗って帰国した。子どもは荷物扱いで頭に荷札が付つけられていたという。土方巽がそのことをテーマに中嶋夏の舞踏の演目を制作した。
夏さんと母がだぶって来るのは何故だろう。母は終戦当時10歳だから7歳ほど夏さんが年下だが、やはり戦前と戦後を生き抜いた共通の強さとしたたかさがある。何もない所から、すべてをゼロから自分で立ち上げて築いていかなければならない。どんなことがあっても絶対に負けない、倒れても必ず立ち上がる、という芯の強さを持っていた。

次号につづく