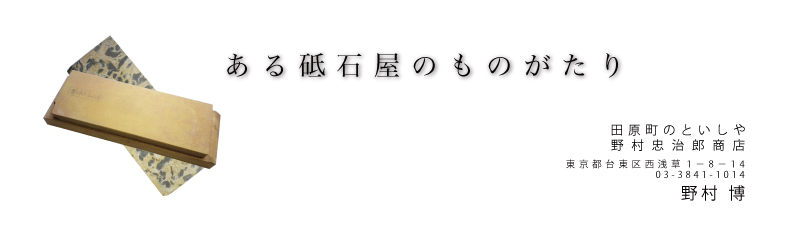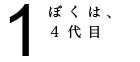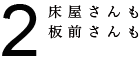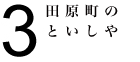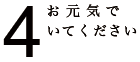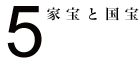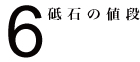きょうだい4人のなかで、ぼくだけなんだ、砥石屋をやるよ、って言ったのは。ぼくも、考えていてね、一番ブラブラしていてもいい仕事でしょ。そしたら、オヤジはね、「お前には、もってこいだ。掃除しなくてもいいからな」って。他の商売とくらべると、多少、品物がホコリをかぶっていても、いいですからね。
オヤジ、笑ってましたよ。ぼくは、言ったんだ。「儲けても、身上を残すようなことはしない。儲けたものは、全部、使っちゃう。そのかわり、オヤジの残したものは、減らさないから大丈夫」って。それが中学生のとき。ぼくは、4代目。
いま、90ですからね。もう、80年近く、やっている。商売の勉強なんて、オヤジの話を聞いていただけ。お客さんとのやりとりを、なにげなく聞いていただけ。山について行っても、ぼくなんか、相手にされなかった。山の人が「また、あの石、出ていますよ」と言うと、オヤジが「ダメだよ。あれは、見かけはよくても、すぐ割れちゃって」なんて答えていたのを、覚えている。
それから、藝大の木彫の関野聖雲先生という、高村光雲の一番弟子が、生徒を5、6人つれてやってくるんですよ。そして、店の土間で、先生がノミをといでね、生徒たちは、見ている。そういうときのやりとりを聞いていた。いやあ、勉強なんか、しなかった。ただ、聞いていただけですよ。
ハタチくらいになったとき、自分でも、少しわかってきたな、と思ったね。お客さんと話すなかで、あちらのいう意味も、求めているものも、わかってきましたよ。

これは、藝大の先生が言ったことだけど、刃物が10挺あれば、仕上げ砥は10丁なければダメだって。うちにも、大工さん以外にも、いろいろな仕事の人が、いろいろな砥石を買いに来たものですよ。
床屋さんが来て、カミソリをとぐ石を買う。床屋さんが休みの日 には、ここが、床屋さんでいっぱいになったものですよ。
三味線の胴は、いい石で磨くと、いい艶がでる。棹を削るのにも、 砥石を使った。茶碗の糸底も、石で磨いた。
もちろん、板前さんも来た。「おかげさまで、おたくの砥石を使ってお客さんが増えました」と言ったものですよ。マグロなんか切っても、あ、これは切れ味がいい、砥石がいい、ってわかるんだ。刀鍛冶屋さんも、宮入さんという人間国宝の人が来てました。刀をとぐんだけど、それは多数の特殊な砥石でね。これは、刃先をとぐ、これは、ミネのほうと、刀の場合、とぐ場所によって、砥石が違う。
そうそう。宮大工さんで、カンナを、仕事の前の日の夜中にゆっくりとぐ、という人がいた。仕事場に、カンナを持って行って削ると、そのカンナ、ちょっと貸して、なぜ、そんなに切れるのって、言われるわけだ。ああ、これが、カンナ用の砥石。で、これは、この石でといだカンナの刃。すごいですよ。ちょっとさわっても、切れるから。いま、これだけとげるウデの人は、あまりいませんね。ぼくも、オヤジにとぐことを習ったけど、すぐ、やめちゃった。
家の包丁をとぐのは、女房。いやあ、そんなにピカピカしてませんよ。

掘り出した石を、使いやすい大きさに切って、削って、面をつけて、売るわけだ。
「田原町のといしや」という店の名前は、オフクロがつけた。その当時、こういう名前は珍しいと言われていたんだよ。いま、天然砥石を専門に扱うのは、うちだけになっちゃったね。ほかにも、道具屋さんで、1丁、2丁と売っているところはあるけど、たいてい、人造砥石になっちゃった。もう、石はほとんど取れない。京都の鳴滝・中山のところは、風致地区になってね。もう、掘れない。そのあたり、砥石なんか掘らなくても、みんなお金持ちだし、それに、紅葉狩りなんかの観光でいいんだ。
いま、石を掘ると、金がかかるんですよ。露天掘りはあまりなくて、炭坑みたいに、枕木を組んで掘っていくんですけどね、掘った山の土は、もとに戻さなきゃならなくなったし、掘る職人も、いなくなった。掘ったり、削ったりすると、石の粉で、珪肺になると言われたりしてね。
以前は、畳屋さんも、砥石を買いに、うちにきていた。畳屋さんの刃物用には、丹波から出るいい石があったけど、それは、ちょっと値段が高かった。関東から出る石は、値段が安いので、よく売れた。ところがあるとき、その土地の人から「ゴルフ場をつくるから、砥石はもう、ダメですよ」と言われてね。
でも、ゴルフ場は始めても、あまり客が、来なかったらしい。砥石のほうが、よかったのにね。

砥石には、とぐ順に、荒砥、中砥、仕上げ砥、とありますが、まあ、かならずしも3回とがなくても、いいんです。いまは、荒砥、中砥は、人造の砥石ですませる。仕上げは、天然、京都の石ですかね、京都の鳴滝あたりから出る砥石、特に中山のものを、オヤジは気に入って、まだ、みなさんが、それほど熱心に売っていないときから、それ一辺倒で売ったんですよ。
ただね、その石は、あまりにも、よすぎた。石が固いんですよ。だから、一般の大工さんには、向かなかった。ウデのいい大工さんじゃないと、使いこなせなかった。
いい砥石っていうのはね、分子が揃っていて、研磨力があるっていうものですね。
昔はね、とにかく、大工さんは、ウデ、カンナ、砥石の3つが揃ってないとダメだ、と言われたものです。ところが、カンナがいいんだろう、ウデがいいんだろう、とは言っても、砥石のことは、言わない。カンナのことは、聞くけど、砥石のことを聞く奴はいないんだ。
昔はね、砥石のおかげで、ウデはあがったし、お客さんも2年先までついたって、言われたものですよ。カンナをつくる名人がいてね、その親方が「砥石は、田原町へ行って買え」って言ってたんだ。だから、ほかの店からは、イヤがられていたな。
うーん。いまは、1日に1人か2人しか、お客さんは来ない。だけど、それでもやってなきゃいけない。みんな、帰るときに「お元気でいてください」って言う。ぼくは「今度、あなたが来るときには、死んでるよ」って言ってやる。だって、もう90だよ。これでもう、お店がなくなっても仕方ないよね。

仕事でお目にかかって、印象の深い人は、彫刻家の平櫛田中さんだ。平櫛さんは、いきなり着流しで、ここへ来た。「どちらさんですか」「桜木町の平櫛だよ」そして、桜木町の家へ来てよ、と言うから、ぼくは、行きましたよ。
ちょっと話して、気に入られた。なぜっていうと、ぼくが「先生、私は砥石屋のせがれで、よくわからないけど、この彫刻が好きです」とある作品のことを指したら、喜んじゃってね。その作品は、みんなにクソミソにけなされたもので、ホメたのは、横山大観とぼくだけだったらしい。
平櫛さん、砥石については、あまりうるさくなかった。「ああ、砥石なんか、刃が切れるようになれば、いいんだ」って調子でね。でも、後になって「死んだあと、どんな砥石を使っていたかって、言われたとき困るから、いいのを買おう」と言いましたよ。
いま、奥にある石で、28×13センチ、厚さ8センチというのが、あるんです。うちが、この石を買ったときは、高いので、オヤジも考えちゃったらしい。そしたら、オフクロが、お金の都合は私がつけるから、買ったら」と言ったんです。
その石を平櫛さんが「売ってくれ」と言ってきたことがあってね。「先生の作品と交換なら」と返事したら「オレの作品は国宝だ。勝手に売れない」と答えるんだ。だから、ぼくもね「この石は、うちの家宝だから、勝手に売れません」と言ってやりましたよ。その後、こういう砥石屋がいるって、自宅の新築祝いのときに、平櫛さん、この話をしたらしいよ。

もう、石も少なくなっているからね、この店にも。仕上げ砥は、エート、1、2、3、4種類くらいだね。荒砥や、中砥は、人造でもいいんだから、1種類しか置いてない。前は荒砥は、九州の大村でも、取れた。中砥は、栃木、茨城、群馬あたりからも出た。もう、取れませんからね。ここで売っているのは、昔取れた石だけ。でも、東京で、これだけ揃っているのは、うちくらいでしょうね。
いや、昔も、砥石屋さんは、そんなにはなかった。東京で、うちみたいな砥石屋は20軒くらい。台東区でも、2軒くらいだったかな。
いま、うちの店のシャッターが半分閉まっているでしょ。これはね、全部開けておくと、5、6人で入ってきて、持って行っちゃうのがいるんです。万引きなんだ。持って行くヤツは、少しは知識のあるヤツですよ。だから、シャッターを半分閉めてある。以前は、もっとお客さんが来てたから、もっと盗られていたかもしれないね。弟が言うんだ。「盗られるくらい、お客の来るほうが、いいんじゃないの」って。
砥石の値段は、安いものは、千いくらからあるけど、高いものは、オープン価格。ぼくは、気分で売るんです。生意気なヤツには、砥石でといでもらいたくないね。買う人によって、値段も違う。ぼくは、損したって売るしね。どうせ、もう先はないんだ。わかりますよ、この人は砥石で苦労しているな、とか。いまだって、お金を貯めて買いに来るから、待っていてください、という人いますよ。いい砥石を使う人は、人間が違う。これが、90歳の結論かな。
(了)