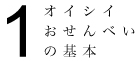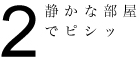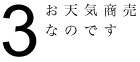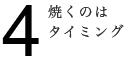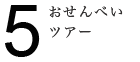まず、いいお米といい天気、ですね。
米は房州の長狭米と地元・富津産のコシヒカリのブレンド。それを精米・製粉して、昔ながらの薪のセイロでふかして、石臼で搗いて、水で冷やしてアク抜きをして、また、搗く---二度搗きをするわけですね---それをカタどりして、そのあと、夏で二日弱、冬で二日、天日で乾燥するんですよ。
で、仕上がったせんべいの生地を、スギの茶箱に入れ、タオルケットでくるんで、二週間---その間、一回、室内で干しなおしをするんです---生地は乾いているようでも乾いていないのです。寝かせている間に、均一にいい乾燥ぐあいにする---それが、難しいんですけどね。乾燥しすぎると割れてしまう、割れるのを怖がっていると、今度は湿度が高すぎて、ふっくらした生地ができないんですよ。
生地の管理が、私にとっては、もっともむずかしいところですね。

生地が乾燥し過ぎて割れるときは、もう、何百枚と割れますね。静かな部屋にいると、ビシッビシッと音をたてて割れるのが分かります。ピシッピシッと聞こえると、ああ、やっちゃったと---泣けますよ。茶箱に入れておいても、北風が吹いたりすると、乾燥するんですよ。乾燥がうまくいくと、いいおせんべいができるんですけどね。
ウチの母親が六十のときに、自分の姉の嫁ぎ先に、修業に行ったんですね ---そこが、三代つづくせんべい屋でして--- 私は、郵便局に勤めていたんですけど、六年前にやめて、母を手伝いながら、仕事を覚えてきました。その母が二年前の秋に亡くなり、私ひとりでやり始めると苦労しましたね。とくにタイヘンだったのが、その生地の管理でした。
このせんべいの大きさは、母が習ってきた大きさ。厚さは、厚いほうがカンロクがあっていいといって、母が厚くしたんですよ。そのぶん、やっぱり難しい。薄いほうが、早く乾燥するし、早く焼けますからね。

生地は、お天気のいいときに、どんどんつくり貯めしておくんですよ。そして、茶箱にしまっておく。そうでないと、梅雨時に乾かす期間がなかなかありませんからね。置けば置くほど、いいせんべいができる---ホント、お天気次第というところもありますね。お天気の長期予報を見て、最低二日つづいていいお天気でないと、手がつけられないですね。やるつもりでいても、予報と違ったりして、急にヤメたりしますよ。お天気商売みたいなところがありますね。
で、その生地を、焼く前の日に、茶箱から焼く分を出して、部屋の棚にのせ、湿気を取り--- それからまた、ココでホイロをかけるというんですが、冬場だと二時間、夏場だと一時間、せんべいを焼く火の上のカゴのなかで乾燥させるんですが---その乾燥も、過ぎるとバラバラになって、焼けない状態になるんですよ。逆に、足りないと、焼いてもふくらんでこない--- エエ、せんべいは、生き物ですよ。

焼くのは、タイミングですよ。いま、手に持っている゛押しがわら゛という焼き物でできた型で、押しながら焼いていきます。押しがわらは、土でできていて、適当な重さがあるんですね。これが、金属製ですと、固いから、おせんべいが割れてしまう。焼くのは、ふくらんでくるタイミングを見て、生地を押してやる --- 早すぎても遅すぎても、いけないんです。
そして、一度焼いたものを、また、焼く --- 二度焼きして、色づけするわけですね --- こんがりキツネ色に。炭は、地元のカシ炭。焼いている途中、ここにある灰で、火力を調節 します。強すぎるとコゲるし、弱すぎると割れますけどね --- ホントに、せんべいは、生き物ですよ。
焼けたら醤油をつけて、冬場だと一時間くらい、夏場だと、もう少し時間をかけて乾燥 させて、出来上がり。 お米の状態から、せんべい一枚できるのに、まあ、二週間かかりますね。
朝、6時ころ、火を熾します。それから、袋詰めまでやると、夜、10時、11時になることもあります。いま、生地づくりから全部やっているところは、あまりないと思いますね。根気のいる仕事ですよ。焼くときは、ずっと座りっぱなし。焼いていて、夏場、熱中症になったこともありますよ。
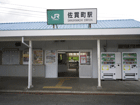



JR内房線・佐貫町駅下車。各駅停車で千葉駅から70分ほど。ひとけの少ない静かな駅。山の方向に、乾いた一本道がある。それを2、3分行くと左に「味処・しらせ」。なんでも、この店のマスターが、南極観測船「しらせ」に乗り組んでいたとかで、いまでも、そのご縁で南極の氷が゛在庫゛。夜、一杯というお客さんには、その氷を提供する。「氷の溶けるときのパチパチというはじける音が、違うね」と、体験者は言った。
そこから7、8分歩くと、右手に大きな醤油樽が見える。ここが、宮醤油店。天保5年創業。以来、醤油一筋。このあたりの温暖な空気とよい水質に恵まれて、天然醸造方式の醤油が、人気。観光客の出入りが目立つ。綾部商店のせんべいも、こちらの醤油を使用している。
そこからまた、6、7分歩くと、左手に駄菓子屋さんふうの気さくなたたずまいの店がある。「手焼きせんべい綾部商店」の看板。おせんべい、ください、と声をかけると、奥からせんべいケースを運んでくる。1枚100円。
そこからさらに坂道を10分ほど上がっていくと、左に綾部商店本店。販売もするが、ここが手焼きの仕事場である。後ろに山が広がり、峠の店、という風情である。店の前の道は、鹿野山のハイキングコースにあたり、リュックサックを背にしたハイカーたちが、おみやげのせんべいを提げて、のんびり歩いている。緩い坂道の上に、白い雲が浮かんでいる。この゛坂の上の雲゛は、ただゆったりと゛せんべいの志゛を、語るのである。

Tel:0439-66-0919
佐貫町店:千葉県富津市佐貫80-1
Tel:0439-80-6333
このおせんべいは、製造を行なっている本店と佐貫町店、見波亭、一品屋(富津市金谷)で販売。また、東京・有楽町の交通会館に全国商工連合会が常設している「むらからまちから館」にチャレンジ期間として六カ月出品、お客さまがついたことから現在も出品・販売されている。