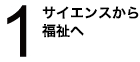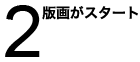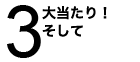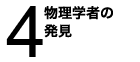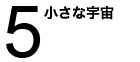日本で万華鏡の作家は、いま、おそらく100人は超えていますよ。だけど、実際それで経済が成り立っている人は、10人はいないでしょうね。1 ケタですかね。…… 世界で盛んなのは、アメリカでしょう。毎年、世界大会があります。流通業者の会、コレクターの会とかありましてね。この作家の若いときは、こうだったとかね …… そういう世界が、成り立っているのです。アメリカ人のつくるものと、日本人がつくるものは、違います。やっぱり、サイズが違う。大きいです。映像についていうと、美意識が違いますね。和の色って、数えきれないくらいあるでしょう。こういう小さな世界で、美しいものをつくるのは、日本のお家芸。万華鏡の映像って、もしかしたら、家紋の名残りでしょうから。
昔、ヨーロッパでは、貴族の奥さま方がのぞいていました。テンションの高いときは、ブルーで気持ちを落ちつかせ、低いときは、赤で励ますとか、まあ家庭の常備薬のような働きをしていたと、聞いています。やっぱり、こちらには、200万、300万という万華鏡があるようですね。たとえば、オブジェクトに、宝石を入れる。宝石だと、見たときの輝きが違う。宝石は、整いすぎてツマラナイという人もいますが、でも、キラキラが違いますよ。魅力的です。
万華鏡は、まだまだ伸びます。広がります。その一つが、医療福祉関係。高齢化社会の現在、デイサービスとかで手芸をやったりするけれど、飽きられるらしいですね。それで、なにかないか、探し探して、万華鏡へきた人がいるんですよ。いまのご老人は、万華鏡を懐かしく記憶している。認知症の方が、一度つくったら、またやりたいといって、施設の人が驚いたと聞きました。万華鏡づくりのいいところは、ホメる要素がたくさんあるわけ。上手にできた、キレイ、色がいい、と具体的にホメられる。サイエンスからアートへ、そして、福祉へです。

ぼくは、神田・佐久間町の産(さん)なんですよ。そのあたり、町工場、職人の家が多かったけど、いま、学校の先生に聞いてみると、あちこちマンションが立って、そこに住んでいる人は、サラリーマン家庭が多いらしいですね。…… で、ぼくは、学校を出て、ニッカウヰスキーに就職した。入ったころは、サントリーに追いつけ追い越せで、ものすごい、働き甲斐のあるところでした。25年間勤めて、43のときに、退職。そのときもう、フツーの人の三人分は、飲んでいましたよ。…… で、なぜ、辞めたかといいますとね …… 正月、あちこちに年賀状を出すでしょう。ぼくは、字がヘタでね、どうすればいいか、というと版画でやるのがいいわけ。だけど、版画でやるとどうしてもハミ出たりして、印刷するとキタナイ気がする。
どうしたものかと、思っているときに、ステッカーを使うことを考えついた。書く。カッターで文字を切る。それを裏返しに貼って、つくる。わかりますか? さかさ文字を書かなくてもいいわけ。そんな版画の材料を東急ハンズに買いに行っていたら、どうするのかと訊くから、こういうのをやるんですと答えたら、1枚のシートでつくる多色刷り版画、というので、特許とれますよ、といわれた。ぼくの家は、化粧箱を製造していて、蔵前の問屋さんに納めていた。学校から帰ると、職人にまじって、箱をつくっていたんです。風呂敷を入れる箱とかを、ね。
ぼくは、中学のときも高校のときも、それをやっていて、ウデのいいほうだったからね。職人の仲間と一緒に働いて、あれこれ考えるのが、好きだったわけ。それで、特許をとって、これを生かすにはサラリーマンをやっていてはムリだろうと思って、ヤメました。そして、デパートなどで、手づくり年賀状教室というのを開いたら、売れるんですよ。年賀状は、郵政省がやるものだから、これで、一生、食いっぱぐれがないだろうと、そのときは思いました。

脱サラはしたものの、最初から店舗を持つような自信も、お金もなかった。それに、そんなリスクもかけられない。ですから、カルチャー教室や百貨店の売り場とかをお借りして、カバンをさげて回っていましたね。デパートの、夏休みの子ども相手の催しとかね。夜なべ仕事で、翌日の人数分の材料をつくって、無店舗販売。当時は、バブリーでしたからタイヘンでしたよ。午前はココ、午後はココとあちこち行きました。そのころ、年末にテレビをみていたら、ベートーベンの第九を指揮する人が、あちこち駆けずり回っていた。同じようなことをやっているなあ、と思ったものです。
そりゃあ、忙しかった。考えて、なにかをつくる。そうそう、年賀状だと正月だけだから、それ以外の季節用に、いろいろやっていたんです。タイル時計とかモーターを使ったものとか、ね。メニューはいろいろありました。子どもたちの評判をみて、いけそうだったら商品化したり、教材として、売り込みに行ったり。いやあ、手づくりだから、タイヘン。年間に、10万人くらいの子どもたちの面倒をみていたんですからね。
ところが、バブルがはじけて、プリンターなんかが現れて、あちこちのイベントがなくなってきた。困ったなあというときに、カルチャー教室の担当者から万華鏡をやりませんか、といってきた。いまさら万華鏡という気もしたけど、食うためには仕方ないしね。浅草橋に行って、紙の筒を手に入れて、ノコで切って、自分でつくってみた。それが始まりです。エエ、今も年に4、5校、台東区内の小学校に教育委員関係のものづくり授業で万華鏡の講師として行きます。「みなさん、ゆっくりていねいにが、ものづくりのコツですよ」と、初めに黒板に大きく書く。終わりに質問タイム。「万華鏡は誰が考えたのですか? それは、どこの国の人ですか?」という質問、多いですね。

万華鏡って、いまや、コミュニケーション・ツールですよ。200年前には、サイエンスだったんです。当時、航海の安全のために灯台のレンズや鏡の研究をしていたなかで、不思議な映像が見えた。それをデザインとして扱っているうちに、世界中に広まった。日本にきたのは、江戸時代といわれています。スコットランドで生まれ、反対側の島国にきて、いまも、新たなアイデアがでるというのは、おもしろいでしょう。ここにある万華鏡は、ハートの型。本体をハート型にしたのはあったけど、これはカプセルもハート型。ハート型だと、曲面が二つ。それに凹みがあって、とんがりもあって、直線が二つあるから、見ていて動きが読めない。規則性がないんですね。
こんなものができたんだけどと、台東区役所のある人に言ったんですよ。そしたら、その人が、f分の1ゆらぎ理論ってご存じですか、って言う。いいえ、聞いたことないです、と答えたんですが、それはどうも、不規則性をあらわしているらしい。よくわからないけど、…… ビルの壁のタイルは、全部同じ白だと圧迫感があるから、ちょっとある部分、色を変えたりする。…… どうも、そういう問題らしい。ぼくは、理論はよくわからないんだけど、それを万華鏡で、創造しているということらしい。あ、これは、セールストークに使えるな、と思った。
ぼく以外、誰も知らない知識で、誰もマネできないものをつくり、世の中に出す。それが、楽しみなんです。ぼくが思いつくころには、同じことを考えている人が3人はいますよ。そう、覚悟してる。なぜって、以前、こんなことがあった。テレビでちょっと見て、おもしろいアイデアだなと思って、その話題の方のところにデンワしてみたら、「お客さんで、デンワされたの3人目ですよ」と言われました。やっぱり、好きな人って、世の中にはいるんだなと思いましたよ。

いま、うちの仕事は98パーセントが万華鏡です。見た方のオモシロイ、驚いた、キレイだ、癒されるという、それぞれの反応が楽しい。 …… これを、覗いてみてくださいよ。宇宙をイメージしたもの、です。突き当たりにツブツブがいっぱい見えるのは、大流星群。…… いろいろなストーリーができるわけね。小さな宇宙ですよ。こちらのキーワードは、漆黒の闇。覗くと真っ暗でしょう。映像が引き立つわけ。万華鏡には、鏡という文字が入りますね。ところが、漆黒の闇になると、鏡の存在が消える。わかりますか? …… そして、こういう見る楽しさを、いかに伝えるか、ですよ。万華鏡の遊び方を教えてあげる。気持ちを落ち着けたいときは、これを上にして、元気がないときは、こう下にして見てください、とかね。ほら、気分が変わるでしょう?
とにかく全部手づくりだから、タイヘンですよ。材料としては、筒、レンズ、鏡、オブジェクト、オイル。筒は、アクリル、木、紙 …… 木でも、これは赤ワインの染み込んだ樽の木。レンズは人間の目で焦点を合わせるために、補正するわけ。鏡は、表面反射鏡というガラスを使う。近所のガラス屋さんで切ってもらった鏡とは、つくりが違うんですよ。オブジェクトのことを、ぼくは「具」といってますがね。いろいろなガラスとか、ビーズとか、ビーズもつないで、一つのアクセサリーとして入れると、繊細、上品な映像になりますし。工夫ですよ、すべて。
いま、ココの店長は、ウチの娘なんですけと、オブジェクトにこだわりを持ってましてね。オブジェクトの一粒一粒に自信があるんですよ。色の配合も、独特の学習法でやっています。自分が私淑している岡山在住の万華鏡作家・百々花さんから、名前をいただいて美百花と申しております。職人気質。妥協しない。親の言うことなんか、まず、聞きません。

創心万華鏡
万華鏡は200年前、物理学者が見たフシギな映像からアートとして広まり、そして、いまや福祉の分野へも。立派なコミュニケーション・ツールです。
創心万華鏡 インフォメーション
「英語で学ぶ万華鏡クラス」
2015年秋よりスタートしました。
バイリンガルのAnna先生と、色や制作のちょっとしたヒントを学びながら、自分だけの万華鏡を作ります。英語とアートに触れる、ここだけのクラスです。季節ごとの新しいテーマと、先生手作りのオブジェクトをご用意してお待ちしております。
2015年12月12日・19日
2016年1月9日・19日
※毎月2回 土曜日に実施
※料金:3,780円(税込)