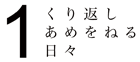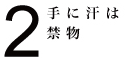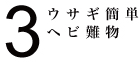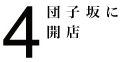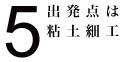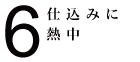弟子入りを希望すると、最初は、断られましたね。「いまは、教えていない」と。ネットで調べたり、新聞とかで取り上げられているのを探したり -- お祭りの屋台でやっているのを見て、話をして、どんなカンジかな、とか。--- 最初に断られた人に、また、連絡しましたら、大阪に来るなら、といわれました。その方が、石割貞治さん。「一回、現場へ来なさい」と。そこで、お話をすると、溶けているあめを見せられました。
これが、すごくアツイ。だいたい、みなさん、この熱いのを知らない、というんですね。この熱いあめを、練って丸めることができるようになったら、もう一度、来なさい、と。余っているあめをあげるから、これをレンジか炊飯器で温めて、やわらかくして、練ってみなさい、と。あめを渡されました。
温めたあめの温度は、80℃くらい。持ってみると、表面は冷めていますが、中は、熱があるんですね。アツイというよりイタイ。手は水ぶくれ、ですね。よく練って白くする。空気を練り込むんです。温かいあめが、冷めて固まるまでが3分くらい。その3分というのは、あめ細工としては、あめを取り出してからカタチをつくるまでの時間なので、実際、あめを練って白くする時間は、まあ、1分弱。初めのうちは、白くなったころには、固まって、カチカチになってしまう。---- 白くなるということは、あめの中に空気の層ができる、ということで、そうなると、急に固まったりしないので、細工がしやすくなるんですよ。
練って、白くして、オダンゴ状に丸くつくる。1カ月半、やりましたかね。だんだん、ヤケドもしなくなった。あめに触れるとき、ぐっと力を入れると熱いですが、力を入れないように、やさしく、しかも、触れる場所を変えていく。そういうことを自然に覚え、指が、勝手に動くようになりました。1日、100個近く、オダンゴをつくり、ああ、なんとか、触れるようになったかなあ、と思って、師匠に連絡したら、「じゃ、まあ、こっちへ来なさい」と。

やっぱり、食べ物を扱うので、手に汗をかくのは、よくないです。手が、あめにくっついてヤケドしやすいし、また、ハサミに塩分がつくので、サビやすくなります。緊張して、手に汗をかくようだったら、教えないといわれました。実際、お客さんの前でつくると、結構、ドキドキするのですが、自分で、汗はかかない、という思い込みをさせて、やりました。
ハサミを扱うので、手にマメができます。マメというより、皮膚が固くなってくるんです。これは、ふやかして、削っちゃう。角質化したほうが熱をカンジませんし、都合がイイのですが、その分、感覚が弱まって、あめが、後どのくらいで固まるか、というのが、わかりづらくなります。
ぼくは、体質的に、あめ細工に向いているほうかな、と思いますね。指先の肉球というか、爪の下の肉のまるみがないんです。生まれつき、指先がヘラみたいに薄い。だから、細かいところが、つまみやすいんですね。昔、ギターを弾こうとしたときは、糸が爪の間に入っちゃって、ギターには、向いてなかったんですけどね。
ハサミは、普通の糸切りバサミです。たとえば、恐竜やサメの歯を、びびっと切ってつくらなければいけないし、だから、自分で使いやすい刃先の形を選んで使います。ハサミを入れるのは、難しいですね。ネバネバしたあめは、パチンとは切れないで、刃先が、入り込んじゃうとか滑るとかして、初めはナカナカ難しい。紙とか平面のものは、切ったことはあるけれど、体積のあるものを切るのは、不慣れなので、必要な分量を切り取れなかったりするんですね。ハサミの扱いはタイヘンです。
分量といえば、あめダマからつくっていくので、分量の配分、バランスが難しい。粘土細工だったら、途中で足すこともできますけどねえ。 --- ええ、で、師匠からは、ウサギ、ツル、小鳥と、基本の3つを、とりあえず教えるから、家で練習してくるようにと、いわれたんです。

ウサギ、ツル、小鳥 -- 師匠がこれをつくるのを横で見ているように、いわれました。こうやって、こうやってって、説明しながらつくっていただけるので、それを見て覚えて家に帰って練習するんですね。説明を聞き、見ている分にはカンタンなんですけど、実際つくるとできないんですね。つくる手順は、わかるんですけどねえ。まあとにかく、ずっと見ていまして、あ、ここを切っているな、とか、一つずつ確認し、家へ帰ってそれを思い出して、こうやったらキレイになるのかなとか、繰り返し、繰り返し、やってみるんです。
ビデオとか写真に撮ったりしてはいけないと、師匠にいわれたんですけど、ぼくも、そう思っていたんです。ビデオを撮ると、撮ることに夢中になり、それで、実は、見ていないんですよ。撮ったことに、安心してしまう。なので、とにかく、その場で見ていようと。メモもとらないで、ずっと見ていました。で、覚えて帰る。家に帰ると、部分部分は覚えています。全体的には、覚えきれないけど。こういうふうに、切っていた、というイメージをアタマの中に入れておいて、やってみる。つぎに行ったときに、同じものをつくるのを見て、再確認して、初めてわかる。自分が、どう違っていたか、同じでよかったか、わかる。それの繰り返しでしたね。
ウサギは、つくるのはカンタンなんですね。作業的には、ヘビのほうが、カンタンそうに見えて、そうではない。ウサギは、なにがカンタンかというと、これは、後になって気づいたのですが、表現しやすいんですよ。つくったとき、お客さんに、それがなんであるか、わからせないといけないのですが、ウサギだったら、耳が大きければ、まあ、ウサギに見えるんですね。
ヘビが難しいのは、最初、伸ばすときに、一気に、こう、ビューンと伸ばすんですけど、あめは温度差で、固いところとやわらかいところがあるので、やわらかいところしか、伸びないんですよ。それを、こう、うまいこと、ちょうどいい状態に練り上げておいて、一気に伸ばす力加減というのが、すごく難しいですね。。

つくるのに、いちばん苦戦したのは、カブトムシですかね。動物をたくさんつくって、4本脚のフォルムが頭に入っているとき、急に6本脚になり、その6本の脚に、頭と胸とお腹の3分割がついている、あのバランスが、うまく、取れないんですね。細いところは、割れてしまうし、脚はキレイにならないし。
あと、やりにくいものは、車、建物、スカイツリー-- なんかは、難しいですね。つくっても、エッジというか、角が出ないで、どうしても、やわらかな丸いカンジになってしまう。パンダも難しいですね。あまり、あめのうえに着色ができないので、柄がよく描けない。カンタンなのは、ウサギ、イヌ -- みんながよく知っている動物は、イメージで、お客さんもそれとわかるので、どうつくっても、あ、イヌだなとわかっていただけますから。
-- とまあこんなふうに、2年間、修業しました。師匠から「もう、そろそろ、東京へ戻ってやったら」といわれました。もう少し、見たり勉強したりしたかったのですが、そういわれたからには帰らなければと、東京へ帰りました。ちょうどそのころ、お台場の大江戸温泉が、江戸の町ふうにやっていて、話題になっていると聞いたので、行ってみました。あめ細工をやっているものですが、とご挨拶して、1日、営業させてもらったら、ブースを設けていただけた。これは、結構、イケました。それが、東京でのスタートです。
団子坂のこのお店は、2008年から。お店兼作業場をつくろうと考えたとき、若者の集まるちょっとオシャレな街、原宿のはずれあたりがいいか、日本ポイ雰囲気のあるところがいいか、まあ、どっちも面白いなと探していて、この近くを歩いていたとき、偶然、このあいている店舗が、あったのです。スゴイめぐりあわせで、よかったですよ。

ぼくは、21歳の時から、東京と千葉のレストランで働きました。そのうち、やはり本場で勉強をと、イタリアへ行きました。向こうでは、お金がないので小さなホテルに泊まると、いろんな国の人がいる。そこで、日本のことを聞かれると、ぼくは、深いところまで答えられない。なぜ、日本人が、イタリアへイタリア料理の勉強にきているのか、と聞かれても、ウーン、好きだから、というくらいしか言えないんですね。
他の国の人は、旅行してみて、いいところもたくさんあるけど、やっぱり、自分の国がイチバンだ。ぼくの国は、こういうところだぜとか、みんな、ちゃんと、話せるんですよ。そこで、あ、日本へ帰って日本のことをやったほうがいいかな、と考えました。ちょうど、ビザが切れて帰るとき、これは、何か始めるのにいい機会だと。そこで思い出したのが、あめ細工です。ぼくは、小さいときから粘土細工が大好きで、あめ細工も、すごくやりたいと思ったことがあったんです。そのとき、他の工芸のことも調べたりして迷ったんですけど、これから学んでいったりすると、すごく時間がかかるんですね。もう、26歳だったので、これでは、いつになったら食えるかなあと、考えたりもしました。
あめ細工は自分がやりたかったものの一つですし、それと、お祭りのとき屋台でやっているのを見ると、工芸とパフォーマンスが組み合わさっている感じに見えたんですね。
下積み生活はもちろん必要ですけど、その本人がどれくらいパフォーマンスできるかが大切なことで、それで、どんどん自分から前に進んで行けるんじゃないか --- それも、一つの後押しになって --- まあ、運よく --- いま、あめ細工をしていると楽しいですし、自分に合っているところがあったな、と。
いや、職業病というほどじゃない、モノづくりの人間はみんなそうでしょうけど、何かを見たときに、あ、これはつくれるかな、これをつくるにはどうしたらいいかなって、考えますね。

やっぱり、コレ、甘いものなので、冬のほうが求められますね。それに、気候的に乾燥しているほうがいい。冬は、つくりやすいんです。お客さんは、夏の倍くらいありますね。
いま、店の休日は、月曜日と火曜日。とりあえず、月曜日は、上野の美術館とか動物園がお休みで、ま、それで、コチラも休日に。火曜日は、あめ細工の材料をつくらないといけないので、ふたりがかりで、その作業をします。
あめの原料は水あめとお砂糖なんですが、あめ細工のあめは、水あめがほとんどです。水あめ9対砂糖1くらいですか。
水あめの水分を鍋で煮詰める。水分が少なくなると、冷えると固まりやすくなる。--- その状態をつくりあげるわけです。時間的には、2時間あれば、ある程度、仕込みはできるんですけど、そのときの気候・湿度によって微妙に違うので、そこに気を遣いますね。
いま、お店には、写真つきのメニューを用意して、それを見て注文していただいて、それを目の前でつくります。そこにないものは、オーダーメイドでいたします。この町自体、ネコが多いからか、ネコの注文が多いですね。
屋台でつくる場合など、しゃべりながらやりますが、口上みたいなのは、ないんですね。これをつくるときは、こういうしゃべり方をしてつくる、というのは、ないんですね。でも、お客さんの注文をうけて、コミュニケーションもとらなくてはいけないし、やはり、間をもたせたいですし、少しでも喜んでいただきたいし、 --- で、喋ります。実際、いいものをつくりたいと思ったら、喋らないで根詰めてつくりたいのですが、楽しそうにつくると、作品にも、それが現れますからね。
とにかくいまは、江戸時代に始まったという、このあめ細工を残していきたい、と思います。やっている方も少なくなってきた。仕事にならない、という面があってヤメていくんだと思いますが、もっと浸透させて、より多くの人に、見て知ってもらいたいですね。
弟子入り希望者ですか? あります。希望の人がくると、師匠がぼくにしたように、まず、一度は、断りますね。

あめ細工吉原
TEL&FAX: 03-6323-3319
E-MAIL:mail@ame-yoshihara.com
日本唯一、世界唯一の日本伝統飴細工の店舗です。
日本伝統の飴細工をたくさんの方々に知ってもらい、楽しんでもらうために今まで前例の無かった常設店舗で飴細工を販売しております。